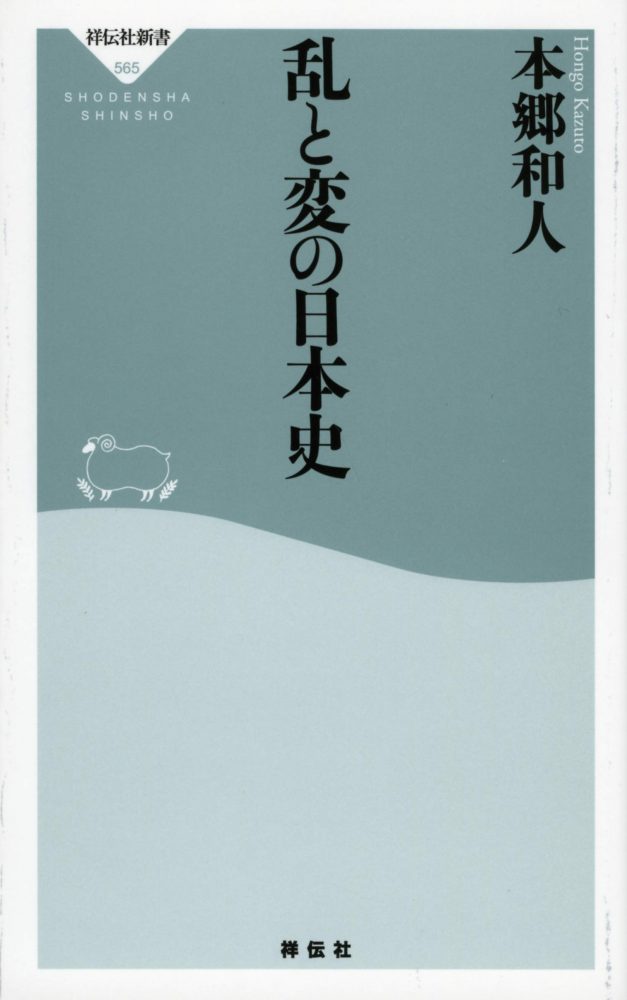12世紀後半から16世紀後半までの約400年、鎌倉時代・室町時代を日本史における「中世」と言います。この中世に、乱と変が多く発生します。
その理由を著者は
中世が「武士の時代」であり、彼らによる異議申し立てが頻発したからです。
乱と変の日本史 p3 はじめに
と述べています。
序 乱と変から何がわかるか
何をもって「乱」「変」「陣」「役」「合戦」と言うか、歴史学上の定義はなく、学問的に決まったルールがないそうです。これを知り、言葉・用語の定義がない学問があるのかと、ずいぶん呆れました。
ですが、筆者は、国全体を揺るがすような大きな戦いを「乱」、影響が現敵的な規模の戦いを「変」と捉えてよいのではないかと考えています。
そうした観点から、霜月騒動は、規模からいえば「乱」、応仁の乱は、規模から「大乱」、観応の擾乱に至っては「擾乱」を使った事例がないため、表現の変更が望ましいと考えています。他にも、関ヶ原の戦いは、同時期に東北と九州で独自の動きが展開されていましたので「慶長戦役」「慶長の大乱」という方が事実に即していると言います。大坂の陣も「大阪城の戦い」の方が状況にふさわしいのではないかと問題提起しています。
学問的な定義やルールがないのであれば、定義やルールを定めて変更していくのが、学会や学者の務めだと思います。
筆者の感覚では「戦争」「役」「乱」「変」「戦い」の順で規模が小さくなっていくように思われるそうです。
本書で取り上げるのは、軍勢と軍勢が戦う教義の戦い、かつ、中世を中心に日本国内で行われたケースです。
乱と変がなぜ起きたのかという「背景」と、誰と誰が何のために戦ったのかという「構図」、どう進展したのかという「経過」、そして何をもたらしたのかという「結果」を明らかにして、考察を進めていきます。
第一章 平将門の乱
平将門の乱とは「武士の時代」の始まりを告げる戦いでした。
武士には2つのルーツがあります。ひとつは、地方で力をつけた在地領主、もう一つは京都から都落ちした貴族です。どちらが武士の本質かは議論がありますが、筆者の立場は前者です。
平将門は「私営田領主」と呼ばれる在地領主です。国家が直接経営した公営田(くえいでん)と対比されます。
当時の律令制では「公地公民」を建前にしていましたので、土地の私有は認められていませんでした。
そうした中、現在の県庁に相当する「国衙(こくが)」が国ごとに置かれましたが、その国衙を相手に税額を決め、半ば土地を所有したのが私営田領主です。
国から国衙に派遣される地方官が国司で、国司には、守(かみ)、介(すけ)、掾(じょう)、目(さかん)が置かれました。こうした役人の中には、任期が終わっても任国に土着し、私営田領主となっていくものが出ます。
背景(なぜ起きたのか)
当時の平安時代にはまともな警察機構はなく、治安も保たれていませんでした。トマス・ホッブズがリヴァイアサンで描いた「万民の万民に対する闘争」状態でした。
私営田は常に狙われていましたので、私営田領主は自力救済のために、武装をはじめ、武士が誕生します。
鎌倉時代になると、武士が鎌倉幕府という権力に守ってもらう関係や、兵の道という武士道が形成されていくようになります。
平将門のルーツ
平将門の先祖は上総国(千葉県中部)に国司のナンバー2として赴任してきた上総介の平氏の一族です。関東は源氏より先に平氏が土着していました。
代表的な平氏は、相模の三浦氏、上総の上総氏、下総の千葉氏、武蔵の畠山氏です。
構図(誰と誰が何のために戦ったのか)
平将門の父・良将は下総の佐倉(千葉県佐倉市)に所領を持っていました。父が若くして亡くなったため、都から将門は戻ってきますが、土地は伯父らによって奪われていました。
将門は佐倉から同じく下総の豊田(茨城県常総市、下妻市)に本拠地を移し、土地を取り戻す戦いを始めます。
承平5(935)年に、源護の息子、伯父・国香を討ち取り、叔父・良兼らとも戦います。源護は朝廷に訴え、将門は召喚命令を受けて京で尋問を受けますが、軽い刑のうえ、恩赦が下されて関東に戻ってきます。
関東に戻ると将門は関東各地で戦いを広げ、承平8(938)には興世王と源経基が足立郡の郡司を襲撃すると、介入して争いを止めることもしました。
国衙に秩序を守る力が無いので、顔役の将門が調停役を果たしたということです。
経過(どう進展したのか)
将門は天慶2(939)に新皇を名乗ります。そして、自ら関東諸国の国司を命じます。将門は朝廷が定めた国司のルールを踏襲して命じていたのです。
本拠としては下総の相馬郡を本拠としていましたが、網野善彦氏によれば、当時の武士は漂流型のため、本拠を移しながら活動していました。
天慶3年に朝廷が動きますが、征東大将軍の藤原忠文が関東に到着する前に、平貞盛や藤原秀郷らによって討たれました。
結果(何をもたらしたのか)
将門には関東独立の志のようなものが認められます。のちに関東人たちが平将門に関東独立の夢を見ることになります。
将門を討った平貞盛ら平氏は関東で力をつけ、伊勢に移って伊勢平氏となります。そして平氏がいなくなったところに入ってきたのが源氏でした。
藤原純友の乱
同じころに起きた藤原純友の乱と合わせて承平・天慶の乱ということもあります。
平将門の乱は2か月で終わりましたが、藤原純友の乱は2年持ちこたえました。ですが、将門のように地域位の人から敬われたり、独立や反抗のシンボルになることはありませんでした。
日本史に与えた影響では、将門の乱の方が大きかったのです。
第二章 保元の乱、平治の乱
保元の乱は崇徳上皇vs後白河天皇、藤原摂関家の家督相続が絡み、保元元(1156)に起きます。
上皇側には源為義、平忠正、天皇側は平清盛、源義朝がつき、上皇側が敗北し、崇徳上皇は讃岐へ流され、源為義と平忠正は処刑されました。
背景(なぜ起きたのか)
1.「武家の棟梁」の出現
保元の乱の背景には「武家の棟梁」の出現があります。
武士団を束ねて、朝廷や貴族の私兵として仕えたのが、源氏と平氏でした。そのボスが武家の棟梁です。
ただし、武家の棟梁になれる人となれない人がいます。源氏の一族であった足利氏は武家の棟梁になれましたが、北条氏のような御家人は棟梁になれませんでした。その違いが何なのかは、納得できる理屈は示すことができていません。
東の源氏と西の平氏が互いに力を得たことが、保元の乱の背景にありました。源氏は藤原本家の傭兵隊長、平氏は上皇の傭兵隊長です。
2.「上皇」の存在
次に重要なのが「上皇」の存在でした。治天の君として君臨する上皇は、家権力、つまりは天皇家の家父長として天皇を凌ぐ力を持ちました。
ヨーロッパでは、王が退位するとただの人になりますが、日本では天皇を降りても実権を握った人がいたのです。
3.地位よりも家の重視
3つ目の背景は、地位よりも家の重視です。天皇や摂政・関白という地位よりも、家が優先されました。権力を握ったのは家父長です。
そして血よりも家が大事でした。そのため、血のつながった実子でなくとも、養子でも良かったのです。血脈よりも、家を継承していくことが重視されたため、当主の座を巡った争いが絶えなかったのです。
構図(誰と誰が何のために戦ったのか)
キーマンとなったのが崇徳上皇です。崇徳上皇は子・重仁親王を天皇に即位させ、治天の君=天皇家の家父長となって権力を掌握したいと思っていました。
ですが、父・鳥羽上皇が治天の君として君臨しており、地位を手放さなかったため、親子間での争いが保元の乱の伏線となります。鳥羽上皇がなくなった時点での天皇が後白河天皇でした。
これに藤原本家における当主をめぐる争いが絡みます。
そしてさらに信西入道(藤原通憲)が介入してきたため、ややこしくなります。
経過(どう進展したのか)
後白河天皇についた信西は、天皇の名で勅命を出します。これに応じたのが、平氏の当主・平清盛と源氏の当主・源義朝でした。一方、崇徳上皇が集めたのが、源為義、源為朝、平忠正らでした。
そして保元元(1156)年7月に戦いが始まります。
結果(何をもたらしたのか)
保元の乱の結果、後白河天皇側が勝利しますが、そのまま平治の乱へ舞台が移ります。
後白河天皇は政治に興味がなく、ほとんど信西に丸投げします。信西は次々に成果を上げ、律令制の幕引きに花を添えました。
この信西の力の源は、後白河天皇の信頼でした。気に入られていることが権力のすべてであり、気に入られなければ権力を失ってしまいます。これが院政の本質でした。
保元の乱の結果、平貞盛はうまみのあるポストを得ました。一方で、源義朝は経済的なうまみのない官職だったため、不満を募らせます。
平治の乱
こうした状況の中で、信西を追い落としたい藤原信頼が源義朝と組んで、クーデターを敢行します。信西は自害に追い込まれます。
これは単なる内乱でした。つまり、どちらが勝っても大した違いはありませんでした。クーデターを聞きつけた平清盛は、兵をまとめて京へ帰還し、源義朝を圧倒します。
平治の乱の結果、平氏が武家の棟梁として唯一の存在となりました。平治の乱自体は大した戦いではありませんでしたが、武士の実力を目の当たりにした貴族たちは、武家の棟梁をきちんと処遇しないと自らの身が危うくなることを感じ、平清盛を迎え入れます。
保元の乱・平治の乱を概観すると、権力・権威・富を独占していた貴族たちが無視できないほど、武士の力が強くなったことが分かります。
第三章 治承・寿永の乱
治承・寿永の乱とはいわゆる源平の争乱のことです。
源氏と平氏が戦った本質については、研究者ですらなかなか答えられません。
この本質を考えるにあたり、中世の国家体制について押さえる必要があります。これには大きく2つの考え方があります。
中世の国家体制に関する2つの考え方
「権門体制論」
ひとつは「権門体制論」です。中世にも日本というひとつの国家があり、トップである朝廷(天皇)を貴族(公家)、武士(武家)、僧侶・神官(寺家・社家)が支えていたとみる考え方です。こちらが主流派です。
公家、武家、寺家は、それぞれの内部の権門勢家を中心にまとまり、世襲原理で連なります。そして、それぞれの経済基盤には荘園があり、そこから税をとるシステムで機能していました。この権門体制論を唱えたのが大阪大学教授の黒田俊雄教授でした。
世襲については、本郷和人「世襲の日本史」が詳しいです。
「東国国家論」
一方、東大教授だった佐藤進一教授が唱えたのが「東国国家論」でした。国家の定義が難しいため東大教授だった五味文彦教授は「ふたつの王権論」を唱えました。
京都を中心とした政権(朝廷)に対して、鎌倉にも将軍を中心とした政権(幕府)があり、両者は並び立っていたという考えです。
いずれの論においても問題となるのは武家の位置付けでした。
背景(なぜ起きたのか)
源頼朝が挙兵した治承4(1180)を前後して木曽義仲や、九州での菊池氏、四国の河野氏、北陸での在庁官人らの挙兵が相次ぎます。
挙兵して行ったのが国衙の奪取でした。それぞれ一地方の支配のために立ち上がったのです。朝廷から見れば反乱です。
平氏政権からすると、朝廷の代わりに反乱分子を討たなければなりません。となると、治承・寿永の乱とは、源平の戦いではなく、朝廷による反乱の鎮圧であり、それが源平の争乱として現れたとみることができます。
第二章でも述べられているように、源氏と平氏は互いに敵でも何でもありませんでした。天皇の命令に従って対決に至りましたが、相手に恨みがあったからではありません。
では源頼朝や木曾義仲が何のために戦ったのかというと、平氏を討つことが目的ではなく、自分の勢力を拡大することが目的だったのではないかと考えられます。
構図(誰と誰が何のために戦ったのか)
源頼朝が房総半島に逃げると、武士たちが次々に臣従を申し出てきます。これが何故なのか、誰も明確な答えが出せていません。
著者なりの解釈では、武士たちは朝廷との関係を変えたかったのです。権門体制論でいうなら、朝廷の下の武家という立場の脱却です。
せっかく開墾した土地を国衙に奪われたくない。土地の権利を守ってくれる人が欲しい。それが天皇の子孫である貴種の源頼朝への期待だったのです。
源頼朝は一種のおみこしです。頼朝もそれをわかっていたから、京都に近づきませんでした。
経過(どう進展したのか)
頼朝はまたたくまに南関東を平定してしまうと、平清盛は朝廷に反旗を翻した反乱分子の源頼朝を討つために大軍を派遣します。そして激突したのが富士川の戦いです。
兵站がしっかりしていなかったため、平氏の戦意は喪失しており、惨憺たる負け方をします。しかし、源頼朝は追討せずに鎌倉に戻ります。
源頼朝は関東での勢力範囲を広げていき、関東八か国を平定します。
源頼朝らが目指したのは武士の自立でした。武家の棟梁が、天皇に並ぶ存在になるということです。言い換えれば、関東が独立するために、戦ったのです。
結果(何をもたらしたのか)
頼朝と関東の武士たちは1対1で主従関係を結びました。「御家人」の誕生です。そして頼朝がもとめたのは、命がけの「奉公」でした。代わりに頼朝が与えたのが「御恩」です。
もっとも重要な御恩が、土地の所有・支配を頼朝の名で認める「本領安堵」でした。これが武士たちが最も欲しかったものです。
第四章 承久の乱
鎌倉時代に入り、承久3(1221)年に、後鳥羽上皇が執権・北条義時追討の院宣を出し、討幕を図ったのが承久の乱です。
義時の息子・泰時らが京都に攻め入って、後鳥羽上皇ら3人の上皇を配流しました。日本史上唯一、官軍が敗れた戦いでした。
さらに掘り下げたのが、本郷和人「承久の乱 日本史のターニングポイント」です。
背景(なぜ起きたのか)
旧体制(権門体制論)の復権を主張する後鳥羽上皇と、関東に新政権を樹立した新体制(東国国家論)を主張する鎌倉幕府の戦いでした。
端的に表れたのが、第3代将軍・源実朝でした。実朝が上皇になびいたため、鎌倉の武士たちは実朝を暗殺してしまいます。
実朝の暗殺の後、公暁の背後に誰がいるかという調査は全く行われませんでしたので、関東の御家人総意での暗殺と考えられます。
その後、源氏の貴公子が殺され、源氏の嫡流の血をひくものがほとんどいなくなります。源氏はいらないという武士たちの意思表示でした。
こうして将軍候補がいなくなると、北条政子は後鳥羽上皇に皇子を将軍として迎え入れたいと申し出ますが断られます。そこで、わずかながら源氏の血を引く藤原本家の九条三寅を迎えて四代将軍となります。
構図(誰と誰が何のために戦ったのか)
後鳥羽上皇は関東にもう一つの政権があると認識していたため、武力で幕府を倒さなければならないと倒幕へ舵を切ります。
鎌倉幕府は安定していなかったため、東国国家論になじめない武士たちが後鳥羽上皇の下にあつまります。
安定していなかったのは、頼朝の死後、誰が幕府のかじ取りをするかで暗闘が展開され、有力者が次々と失脚していきます。そして残ったのが北条義時でした。
梶原景時の失脚、比企能員、畠山重忠、和田義盛の滅亡へと続きます。こうして政務・財政を担当する政所、軍事・警察・御家人の統率を担当する侍所のトップを北条義時が抑えることになるのです。
こうして台頭してきた北条義時を不快に思ったのが後鳥羽上皇でした。後鳥羽上皇は非常に優れた治天の君でした。出たとこ勝負の後醍醐天皇とは異なり、きちんとした方法論にのっとって戦いました。
経過(どう進展したのか)
後鳥羽上皇は承久3(1221)年に北条義時追討の院宣を出すと、武士を集め鎌倉に軍勢を派遣します。
承久の乱の構造は単純で、北条義時を討って幕府を倒せば後鳥羽上皇の勝ち。後鳥羽上皇の意志をくじけば北条義時の勝ちでした。
結果(何をもたらしたのか)
京都が制圧されると、後鳥羽上皇は今後朝廷は一切の軍事力を持たないと記した院宣を発します。実際、承久の乱のあと、幕末に官軍が作られるまで、軍事力を持ちませんでした。
そして、後鳥羽上皇ら3人の上皇は配流され、天皇が無理やり皇位から引きずり降ろされ、後鳥羽上皇の直系子孫が排除されます。
重要なのは、天皇の存在が武力によって否定されたことでした。これによって、権門体制は完全に潰えたと著者は考えます。関東の独立が成立したのです。
以後、鎌倉時代を通じて、朝廷は天皇が替わるたびに幕府にお伺いを立てることが慣例となりました。その中でも、後鳥羽上皇の直系子孫の即位は認められませんでした。
幕府に没収された荘園は3000。それが関東の武士たちに与えられ、幕府の勢力は西国にまで広がります。
幕府は朝廷が担っていた役割を果たすことになり、御成敗式目(貞永式目)を制定し、法による統治をはじめます。御成敗式目は室町時代に至るまで有効性を失いませんでした。
霜月騒動
幕府には、武士の利益を第一とする勢力と、統治者としての撫民の思想を持つ勢力がおり、次第に対立します。前者を代表するのが平頼綱(御内人)で、後者を代表するのが安達泰盛(御家人)でした。
教科書的には、御内人と御家人の対立が激しくなり、御内人の平頼綱が御家人の安達泰盛を滅ぼしたのが霜月騒動、と解釈されます。
しかし、霜月騒動の本質は、御家人を第一と考える平頼綱と民を含めた国全体に責任を持つべきと考える安達泰盛の戦いだったというものです。
霜月騒動の結果、佐藤進一先生は北条氏の得宗体制が強まったと主張しましたが、著者は御家人第一が徹底したと考えています。この解釈にたつと、債権・債務の放棄を命じた徳政令の意味が分かりやすくなります。
永仁の徳政令は、御家人さえ守ればよいというものでしたので、御家人以外の利益は全くありませんでした。この徳政令は鎌倉幕府が滅亡するまで適用され続けます。
そして、全国の政治を行うことを放棄したため、鎌倉幕府は次第に民の信用・信頼を失い、崩壊に至ったのです。
第五章 足利尊氏の反乱
足利尊氏が2回起こした反乱を指しています。1回目が元弘3(1333)年の鎌倉幕府への反乱。2回目が建武②(1335)年の建武政権への反乱です。
元弘の変の際には、後醍醐天皇は隠岐島に流されますが、護良親王がゲリラ戦を展開し、令旨を出して土豪を集めます。土豪は御家人になれなかった武士たちです。
元弘3(1333)年、隠岐島から脱出した後醍醐天皇は船上山で挙兵します。鎌倉幕府は足利高氏に後醍醐天皇捕縛の命を発します。
その高氏が篠村八幡宮まできたとき、突如として後醍醐天皇へ味方することを宣言し、全国の武士へ命令書を送ります。
これに応えた佐々木導誉らによって、1か月後には六波羅探題が落ち、新田義貞が鎌倉を攻撃し、北条氏一族を自害に追い込んで、鎌倉幕府を滅ぼします。
倒幕にあたって大きな役割を果たしたのは、足利高氏の命令でした。源氏一族のトップであり、北条氏に次ぐナンバー2の地位にあった高氏の反旗によって御家人たちは動きました。後醍醐天皇では動かせなかったのです。
御家人にしてみたら、北条氏を倒し、足利高氏が新たに将軍か執権について、幕政を運営すると思っていたのでしょうか、建武の新政が始まります。
背景(なぜ起きたのか)
元弘3(1333)年6月に始まった後醍醐天皇による建武政権は、土地の所有権を白紙に戻し、綸旨によって安堵するなど、これまでの慣習や武士を無視した政治を行い始めます。
すると当然のように全国で武士たちの反乱がおきます。反乱の中で大きかったのが北条氏の残党による中先代の乱です。足利尊氏が反乱を起こさなくても、誰かが武士をまとめて大きな反乱につながっていたでしょう。
足利尊氏は鎌倉を奪い戻すために京都を出発します。その際に後醍醐天皇に征夷大将軍を求めますが、はねつけられます。
構図(誰と誰が何のために戦ったのか)
討伐に向かったものの、武士たちを味方につけることができず、敗北します。そこで、足利尊氏は自分の責任で次々に本領安堵、新恩給与の文書をばらまき始めます。
この時点で、尊氏は天皇から任命されなくても、事実上の征夷大将軍でした。源頼朝と同じく武士たちに土地を配分したので、源頼朝と同じ立場になったのでした。
ここに至って、後醍醐天皇は足利尊氏を謀反人とし、新田義貞に討伐を命じます。このため、足利尊氏は建武2(1335)年に反乱を起こします。
経過(どう進展したのか)
京都へ逃げる新田義貞を追いかけるか、このまま鎌倉に居座るかで、足利尊氏と弟・足利直義の意見が分かれます。
結果としては、足利尊氏は京都に上り、北小路室町に幕府を開きます。
この時点で、東国国家が朝廷を飲み込む形で、新しい権力を作ろうとしたとみることができます。
結果(何をもたらしたのか)
足利尊氏が京都に幕府を開いた理由の一つは経済でした。鎌倉幕府は土地に根差したものでした。質実剛健を旨とする倹約政策ですが、江戸時代の三大改革に出てくる考え方です。平清盛のような日宋貿易を進めて経済の活性化をはかるものとは方向性が違います。
承久の乱のあと、国外から大量の宋銭が流入し、日本に貨幣経済の波が押し寄せました。これは13世紀中頃までに確立し、日本各地で商取引が活発化し、経済が活性化しますが、土地を第一とする鎌倉幕府の政治は大きく揺らぎます。
武士といえども欲しいもののために、土地を手放す者が出てきたのです。鎌倉幕府は貨幣経済の進展に追いつけなかったのです。経済においては、京都は流通の中心でした。足利尊氏は京都を抑えなければ、経済の制御ができないことがわかっていたのでしょう。ですから、京都へ上ったのです。
一方で、室町幕府は鎌倉幕府が作った御成敗式目などの法律をそのまま踏襲します。つまり、鎌倉幕府の否定ではなく、認めたうえで作られた政権であり、鎌倉幕府の延長上にあったのです。
第六章 観応の擾乱
南北朝の対立が絡んでややこしく見えますが、室町時代の観応元(1350)年から観応3(1352)年に起きた、室町幕府の内部抗争です。
足利尊氏の執事(家宰)高師直と足利尊氏の弟・足利直義が争い、高師直が敗死、ついで尊氏と直義が戦い、直義の死によって終わります。
南北朝の動乱は各地の武士を巻き込んで全国化しますが、観応の擾乱はその中で起きました。
背景(なぜ起きたのか)
全国の武士は尊氏党と直義党に分かれて戦います。九州では南朝を含めて三つ巴の戦いとなりました。
実は、これは現地の都合でした。それぞれの勢力を伸ばすことが目的であり、どの陣営に入るかは二の次です。単にどっちに付いた方が得か、自分の利益になるか、出世できるかという目論見で動いていました。
一方で、足利尊氏は流通を抑えるために京都を目指し、足利直義は従来の住み分けを目指していましたので、根本的に異なる考えでした。どちらかが滅びるまで戦わざるを得なかったのです。
足利尊氏と直義の兄弟は仲が良かったと言われます。尊氏は軍事を担当し、直義は政治を担当しました。体制は二頭政治だったのです。
将軍権力の構造の定説は「将軍権力の二元論」です。主従制的支配権(軍事)と統治権的支配権(政治)の二つを保持しているとするものです。
このうち、主従制的支配権を行使するのが武家政権の主で、天下人の第一条件でした。軍事主導であるのが、武家政権の本質だったのです。
構図(誰と誰が何のために戦ったのか)
尊氏と直義は個人的には信頼しあう関係でしたが、システム的には権力が二つに分断され、不自然でした。それぞれの周囲に人が集まり、権力争いが始まります。
尊氏と直義の二頭政治が立ち行かなくなり、周辺勢力を巻き込んだ総覧となったのが観応の擾乱でした。
二つに分かれた権力は、第2代将軍・義詮のもとで再び一つになります。
経過(どう進展したのか)
高師直が率いた軍勢は当時最強で、南北朝の動乱期には室町幕府軍の切り札でした。新田義貞、北畠顕家を破ったのは高師直の軍勢でした。
その軍勢に戦いを挑んで、足利直義は高氏一族を滅ぼします。しかし守護大名の幅広い信望を集めきれず、京都から関東へ下向します。そして尊氏の軍勢と戦い敗れると鎌倉に逃れて、急に亡くなります。
直義が率いた軍の主体は山陰の山名氏でした。山名氏は室町幕府の仮想敵になります。
結果(何をもたらしたのか)
観応の擾乱の結果、日本列島はとりあえずひとつになります。脆弱でしたが、東国国家が解消され、幕府勢力が西国までにひろがり、日本列島を覆ったのです。
第七章 明徳の乱
明徳2(1391)年、守護大名の山名氏清、満幸らが、室町幕府に対して起こした反乱です。この明徳の乱を読み解くと、応仁の乱を簡単に理解することができます。
第3代将軍・足利義満は強大な山名氏の勢力を抑えるために、山名氏一族の内紛に介入します。これに山名氏清、満幸らが挙兵し、山名氏の敗北で終わります。
山名氏の領国は11か国(全国66か国の6分の1を持っていたため六分一殿と呼ばれていました。)から3か国になります。
背景(なぜ起きたのか)
鎌倉時代の守護は、御家人への軍事指揮権はあっても、家臣化はできませんでした。一方、室町時代の守護大名は、家臣化だけでなく、徴税権なども握ったため、農業生産力の向上とともに、大きな力を持ったのです。
強大化した守護大名への対処、力を削ぐことが室町幕府の政策となり、明徳の乱の背景にありました。
構図(誰と誰が何のために戦ったのか)
明徳の乱の起きる時点で、三管領四職の体制を整えていました。三管領は、細川氏、斯波氏、畠山氏、四職は赤松氏、一色氏、山名氏、京極氏です。
こうした室町幕府の骨組みを作ったのが、細川頼之でした。
山名氏は山名時氏の時に山陰地方に勢力圏を拡大します。当時は日本海交易が盛んだったため、非常に豊かな国を有しており、経済力によって力を得ていました。
山名氏が京都に攻めてくるときに、防波堤となったのは赤松氏と細川氏でした。赤松氏と細川氏は仲がとてもよかったのです。
こうして、山名氏vs赤松氏・細川氏の構図ができます。
貞治5(1366)年、貞治の変がおき、斯波氏が失脚します。反斯波派が佐々木導誉と赤松氏でした。佐々木氏の支流が導誉の京極家で、京極と赤松は密接な関係でした。この時、導誉が連れてきたのが細川頼之でした。
構図は、山名氏・斯波氏vs赤松氏・細川氏・京極氏に変化します。
斯波氏は越前の守護でしたが、隣接する一色氏とは仲が悪く、細川頼之は一色氏を起用します。
こうして、構図は山名氏・斯波氏vs赤松氏・細川氏・京極氏・一色氏になります。
畠山氏以外の三管領四職がすべて入りました。
細川頼之は導誉と赤松氏の推薦で管領となり、政権運営を進めます。
経過(どう進展したのか)
斯波氏・山名氏を中心とした反細川勢力により、頼之は失脚します。康暦元(1379)年の「康暦の政変」です
頼之は四国に戻りますが、力を蓄え、第三代将軍・足利義満に招かれて、政界に復帰します。再び実権を握った細川頼之は、強大な守護大名や自分を失脚に追い込んだ政敵を粛清していきます。
そして、山名氏が標的となります。山名氏の軍勢は強力でしたが、幕府軍はかろうじて勝利をおさめます。
結果(何をもたらしたのか)
細川頼之は足利義満の後見人をしていました。丸抱えで義満を育てたのでした。そして義満を担いで室町幕府を運営します。
細川頼之が関わった重要な政策は、1.明徳の乱、2.南北朝の合一、3.東日本の切り離し、4.幕府の京都支配の徹底でした。
細川頼之により、東日本を切り離してミニマムな形で幕府を運営するという現実路線に転換します。
土岐氏、山名氏についで狙われたのが大内氏でした。応永の乱です。この乱の結果、堺は細川氏のものとなります。
第八章 応仁の乱
応仁の乱は応仁元(1467)から文明9(1477)まで11年にわたって続いた大乱です。
教科書的には、管領である畠山氏・斯波氏の家督争いと、足利将軍家の家督争いに、細川勝元と山名宗全が介入して起こった戦いと説明されます。
実態が知られていない応仁の乱ですが、呉座勇一氏「応仁の乱」によれば、本質は二つの大名連合の激突であり、室町幕府の政治体制そのものに原因があるとされます。
しかし、著者は応仁の乱は室町幕府内の長きにわたる政治抗争の結末にほかならず、第七章で述べた構図を引きずり、負け組(山名氏、大内氏、土岐氏)が勝ち組(細川氏、赤松氏、京極氏)にリベンジを挑んだ戦いとみています。
背景(なぜ起きたのか)
教科書では、応仁の乱がおきたため、足利将軍家が没落したと書かれますが、順序は逆です。
足利将軍家の権威・権力が失墜したため、応仁の乱がおきました。
応仁の乱の前、力を持っていたのは三管領の畠山氏でした。山名宗全の父・時熙も同時期に宿老を務めており、畠山氏と山名氏は良好な関係にありました。
細川氏は赤松氏が将軍を弑逆(嘉吉の変)したため、政治的発言権が相対的に下落します。
こうした中、畠山氏の家督争いが応仁の乱の引き金となったため、当時は「畠山一族の乱」と呼ぶことがありました。
構図(誰と誰が何のために戦ったのか)
畠山一族の乱は、山名氏と細川氏が幕府の主導権をめぐって争う戦いへ発展します。
山名宗全には大内氏、土岐氏、一色氏などが加わり、細川勝元には従来からの赤松氏・京極氏が加わります。
これに将軍家の家督争い(義視と義尚」が絡み、全体像が出来上がります。
経過(どう進展したのか)
構図は明徳の乱、応永の乱とほぼ変わらない陣容となります。
足利義満時代の勝ち組が東軍に、負け組が西軍に加わっていることが分かります。
つまり、応仁の乱の本質は室町幕府の政治的な主導権争いです。
こうして始まった戦は、細川勝元と山名宗全が亡くなった後もずるずると続きます。
結果(何をもたらしたのか)
11年間の乱を通じて、足利将軍家に全く力がないことが白日の下にさらされました。
また、守護大名は将軍の無力を知り、地元に引き上げてしまいます。
明徳3(1392)年に、鎌倉公方が治めていた関東と東北、九州探題が置かれた九州は、幕府直轄の直接統治の対象外でしたので、応仁の乱のときに戦っていたのは、京都で暮らしていた守護大名の軍勢たちでした。
ですが、そうした守護大名も地元に戻っても座る席のない守護大名もいました。下剋上が各地で起きていたのです。
一方で、関東・東北・九州の守護大名の多くは戦国大名に転身することに成功しています。京都に縛られず、地元に張り付いていたためです。
応仁の乱の後の室町幕府は、細川政権になりました。この点からも、応仁の乱は、細川氏率いる東軍の勝利で終わったのです。
平安時代から続く荘園制のもと、土地支配は重層的に行われており、誰も独占的に土地を支配していない状態が荘園であり「職の体系」と言われるものでしたが、その体系を戦国大名が根本的に変えました。
第九章 本能寺の変
著者は陰謀論を支持していません。
明智光秀は、武士たちを味方につけるために、将軍や天皇から命令されたことを実行したに過ぎない、と説得するのが効果的ですが、そうしたことを発していないことからも、したくでもできなかった、つまりは単独犯だということなのです。
織田信長は明智光秀に殺されなくとも、いずれは誰かに殺されたでしょう。信長の人生を見ると、裏切られ続けた人生だったからです
背景(なぜ起きたのか)
なぜ信長は裏切られ続けたのか。
それは信長の治める空間が広くなりすぎたからです。戦国大名の空間認識は、自国にとどまり、自国の枠を超えることはありませんでした。
一方、信長は様々な国の人を用いるようになり、封土を変える国替えも頻繁に行いました。時代に二歩も三歩も先をいっていたのです。
それぞれの国の空間を超えると、どの家臣も地縁中心の人間関係を破壊するため、精神的不安に陥ります。仲間だから裏切らないというルールを破ることにもなります。
結果(何をもたらしたのか)
信長の政権は、信長のカリスマがあっての政権でした。信長が作り上げた政治システムは、信長一人が専制君主として君臨する不安定なものでした。そのため、息子の信忠が生き残っていたとしても、状況は変わらなかったでしょう。
第十章 島原の乱
江戸時代の寛永14(1637)年から寛永15(1638)年にかけて起きた大規模な反乱です。
乱の本質については複数の見方があります。ひとつはキリスト教信者による一揆、ふたつめが百姓一揆、三つめが浪人となった武士たちの反乱です。
背景(なぜ起きたのか)
一向宗はキリスト教と似た部分を内包していました。一向宗もひたすら阿弥陀仏に帰依して南無阿弥陀仏と唱えれば、西方浄土に往生できると説いていたからです。
阿弥陀仏の前での平等を説く教えは、国を超えて横につながります。もともと、農村ではピラミッド型の上意下達の関係ではなく、地主・名主、本百姓・脇百姓、下人という三つの階層はそれぞれ横につながっており、突出したリーダーが生まれにくい構造となっていました。こうした村落の構造は一向宗の布教に好都合でした。
戦国時代、自立性を高めた村落共同体は「惣村」に発展していきました。規模が拡大すると惣荘となり、国単位になると惣国が誕生します。例えば、加賀国では一向宗が国を支配しました。
島原の乱は、一向一揆と類似した一揆の形態として、平等を求める最後の戦いだったと、著者は考えます。
構図(誰と誰が何のために戦ったのか)
村落共同体のつながりに、宗教という一向一揆と同じスタイルを持ち、そこに浪人たちが加わり、神の前での平等というキリスト教的価値観の象徴として、天草四郎を担いで戦ったと言えます。
結果(何をもたらしたのか)
江戸時代になると、宗派ごとの自己主張はなくなり、江戸幕府によって牙を抜かれて、力を削がれていました。
そして、檀家として寺に所属することでキリシタンでないことを証明させる寺請制度により、寺は末端の役所のような役割を押し付けられます。
寺は檀家とのかかわりの中で存続することになり、檀家が亡くなると寺の僧侶が葬儀を行い、寺の墓地に埋葬するのが通例となりました。人間の死を一手に引き受ける、葬式仏教が生まれました。
新たな哲学を内包するような壮大な宗教理論が出る素地は失われ、宗教は力を失っていきます。宗教が機能しない日本の土壌は、江戸時代にほぼ基本が出来上がりました。
兵農分離についても、島原の乱のころにはだいたい収まりがついていました。浪人たちにほぼ就職のチャンスがなくなったことを意味していました。
江戸幕府によって士農工商の身分が確立し、封建制の完成形を見ることができます。
江戸幕府は、武士を村落共同体から完全に切り離す政策を展開し、武士は江戸時代を通じてサラリーマン化していきます。
結 日本史における「勝者」の条件
武士の時代を終わらせたのは、1877年の西南戦争でした。
西南戦争は、武士の軍隊vs百姓や町民を含む徴兵軍・政府軍の戦いでした。後者が勝利し、身分としても存在としても武士がいなくなりました。
武士の時代700年間を俯瞰すると、次のようになります。
- 天皇の下の一つの権門として位置づけられていた武士が自立し、東国に政権を打ち立てます。
- 東国政権は京都の朝廷を飲み込みますが、関東や東北を切り離して小さめの国家をつくります。
- 政権争いに端を発した10年に及ぶ乱のあと、バラバラとなります。
- 全国的な争いののち統一されますが、その過程で宗教勢力は排除され、武士はサラリーマン化します。
- そして、武士の手によって、武士の時代を終わらせます。
勝者と敗者を分けたものは、日本の歴史のトレンドに乗った者が勝つというものです。時代・社会の要請に忠実なものが勝つのです。