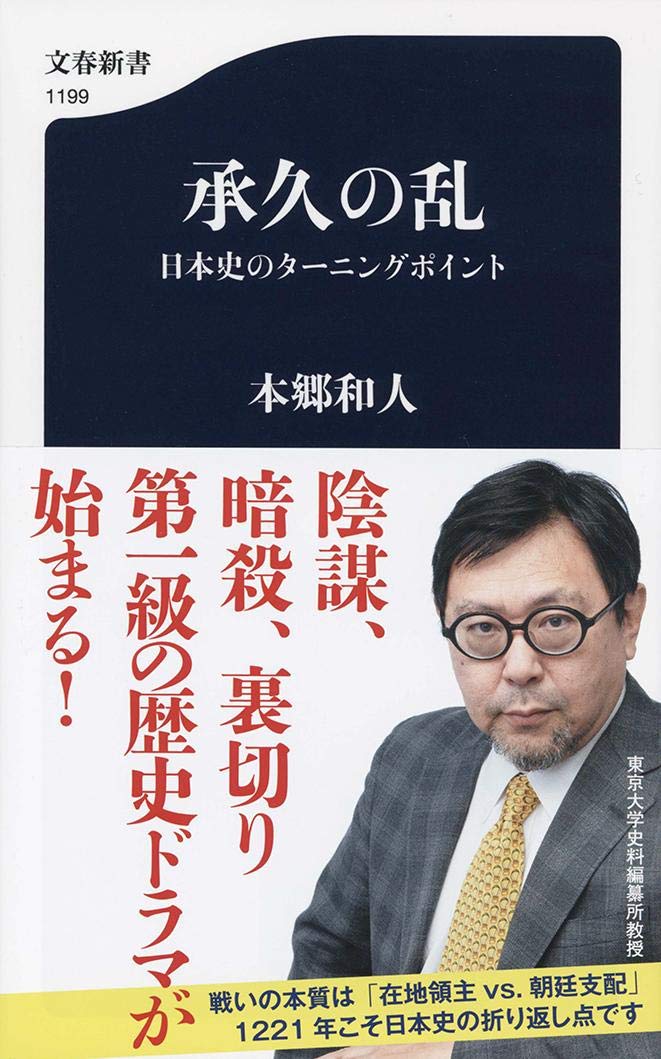本郷和人教授の本は結論や考えを勿体ぶらずに示してくれるのがとても良いです。
分かりやすくを心がけていらっしゃるのも端端からも読み取れます。
学者然とするのは簡単ですので、初学者でもわかるように書こうという姿勢こそが、学者全員が本来持つべき姿勢だと思います。
こうした点も本郷和人教授には好感が持てます。
日本史最大の転回点
日本史の「中世」には乱と変が多く起きました。時期的には、12世紀後半から16世紀後半までの約400年、鎌倉時代・室町時代です。
この期間の乱と変を取り上げたのが、本郷和人氏による「乱と変の日本史」です。同書でも承久の乱は取り上げられていますが、本書は承久の乱を掘り下げた内容となっています。
鎌倉時代の承久3(1221)年、承久の乱がおきます。後鳥羽上皇が鎌倉幕府の実権を握っていた北条義時の追討を命じました。
しかし、戦争としての承久の乱は、鎌倉幕府側の圧勝で終わります。関東から京都に向かった幕府軍のほぼワンサイド・ゲームとなります。
承久の乱の最大の見どころは戦争が始まる前段階にありました。
承久の乱こそが、日本史最大の転回点のひとつだと考えています。
ヤマト王朝以来、朝廷を中心として展開してきた日本の政治を、この乱以後、明治維新に至るまで、実に約六百五十にわたって、武士が司ることになったのです。
また、地理的にも、近畿以西がつねに東方を支配してきた構図がここで逆転し、東国がはじめて西を制することになりました。それは田舎=地方の在地勢力が、都=朝廷を圧倒した最初のケースでもあるのです。
承久の乱 日本史のターニングポイント p4
承久の乱は、教科書的には、次のように解説されます。(『詳説 日本史』山川出版社)
- 承久元(1219)年、後鳥羽上皇と連携をはかっていた将軍・源実朝が公暁に暗殺されると、朝廷と幕府の関係が不安定となる。
- 承久3(1221)年、後鳥羽上皇は畿内・西国の武士や大寺院の僧兵、北条氏の勢力増大に反発する東国武士の一部を味方にし、北条義時を追討する兵を挙げる。
- しかし、東国武士の多数は源頼朝の妻・北条政子の呼びかけに応じて、戦いに臨んだ。
- 幕府は北条義時の子・泰時、弟・時房らの軍に京を攻めさせ、1か月ののち、圧倒的な勝利を得る。
- 後鳥羽上皇、順徳上皇、土御門上皇が配流される。
- 朝廷と幕府の二元的支配の状況が変わり、幕府が優位に立ち、皇位の継承や朝廷の政治にも干渉するようになる。
鎌倉殿の13人
2022年の大河ドラマ「鎌倉殿の13人」で北条義時が主人公となることもあり、承久の乱は注目されました。
同じく承久の乱を扱った本として、坂井孝一「承久の乱-真の「武者の世」を告げる大乱」があります。比較して読まれると一層理解が深まると思います。
社会に浸透してこその歴史学
「あとがき」に印象的な文章がありました。
日本史研究者にはまだまだ頑迷なところがあって、「一般の人に向けて本を書くなど、良心的な研究者のなすべきことではない」と本気で思っている人がたくさんいます。ぼくは社会に浸透してこその歴史学だ、と思っているので機会があればせっせと本を書いているのですが、こういう行為は「研究実績」とは認められないのが現状です。
承久の乱 日本史のターニングポイント p214
この文章には大変驚きました。
大学に所属する歴史学者は国公立であれば全額、私立であっても一部は税金で給与等が賄われています。研究費などはほぼ税金でしょう。
税金を使った研究や教育が、一般の人に向けて還元されないのが大変おかしいことに気付いていない歴史学者が多いことに驚いたのです。
一般の人でない専門家(歴史学者)内での内輪ウケを楽しんでもらうために税金を投入しているわけではありません。
税金を投入して得られた成果は、一般の人に向けて還元することを常に考えるのが、税金で賄われている方の責務だと思います。
一般への還元ができないなら、別の道を歩めばよいのです。公的性格の強い大学や研究機関でなくとも、研究はできます。それこそご自身で任意団体を作れば良いのです。誰も文句は言いません。
一般の人に向けて還元する方法は様々ですが、本郷和人教授のように、一般書を積極的に書くということも、還元方法の一つです。
大学の教員は偉くなんかありません。自分の生活の糧や研究資金が何を原資にしているかを真面目に考え、仕事に取り組み、成果は社会へ還元して頂きたいと思います。
第一章 「鎌倉幕府」とはどんな政権なのか
源頼朝を棟梁と仰ぎ、自分たちの権益、特に土地の保障(=安堵)を得るのが、鎌倉幕府の本質でした。
土地の安堵が「御恩」であり、その代わり頼朝の命令のもとで戦うのが「奉公」です。
これを受け入れて頼朝の直属の子分となったのが「御家人」です。
保障人である源頼朝と主従契約を結んだ仲間たちが、東国に築き上げた安全保障体制です。
つまり「頼朝とその仲間たち」の政治体制です。
土地を守るには
教科書によると
- 古代の日本に中国から律令制が導入
- 土地は公=天皇のもの
- ひとりひとりに区分田を与える
- 租庸調などの税を納めさせた
これを著者は実態からかけ離れたフィクションと考えます。
朝廷側の「べき」論で、そもそもそも朝廷の支配が及ぶ地域は10世紀になっても百万町歩にも及びませんでした。
朝廷が支配しているところから取れるだけ税を取る収奪的な支配だったため、「逃亡」「浮浪」となる農民が続出しました。
律令制はすぐに行き詰まります。
天平15(743)年に墾田永年私財法が出され、開墾した土地は自分のものにしてよくなります。
その私有地が「荘園」と呼ばれますが、その土地を守るのも大変でした。
自分の土地を経営する人を「在地領主」と呼んでいましたが、敵は二つおり、一つは他の在地領主、もう一つが地方の役所である「国衙」でした。
国衙はやっかいで、「公地公民」の建前は維持されているため、いつ何時没収されるかわかりませんでした。
これへの対抗は大きく二つです。
一つは自ら国衙の下っ端役人になること。もう一つが「寄進」でした。上の影響力の強い者を頼るやり方です。
各地で強い親分の利益集団が形成され、実力や権威で抜きん出たのが平氏と源氏でした。
武士の誕生
武士の誕生には長年の論争があります。
ルーツが都か田舎かです。
著者は「田舎の武士」を重く見ています。
中央政治で源平に代表される武士の台頭のきっかけを作ったのは信西でした。
その後、治承・寿永の内乱=源平の戦いが起きます。
この戦いは、武門同士の戦いではなく、在地領主対朝廷政権の戦いと考えられます。
戦いの結果、それぞれの土地での在地権力を確立した、と著者は考えています。
源頼朝は、苦労を分かちあった安達盛長や河越の豪族・河越重頼、伊豆の領主・北条時政、頼朝の乳母・比企尼の妹を母に持つ下級貴族・三好康信、房総半島に逃げてからの味方である千葉常胤、上総広常、武蔵の畠山重忠ら、初期の鎌倉幕府で重要な人々を重用します。
そして富士川の戦いで決定的な局面を迎えます。
京に軍を向かわせようとした源頼朝の前に、千葉常胤、上総広常、三浦義澄らが立ちはだかり、止めたのです。
関東には源氏の佐竹氏を含めて頼朝に従わない者がいるので、それをまずは平らげるべきだということでした。
関東の在地領主が頼朝に求めたのは、東国での新しい秩序でした。在地領主の権利の保障を最優先に求めたのです。
武士の殺生感覚
武士とそうでない人を分ける違いは、殺生に対する感覚ではないかと言います。
鎌倉時代後期に描かれた「男衾三郎絵詞」からは、武士とは生きるために他人の命を奪うことについて何にも思わないという荒々しい感覚が読み取れます。
鎌倉幕府の血なまぐさい権力闘争はこうした殺生観を踏まえるとよく理解できます。
鎌倉武士とは
各国衙では国司の任期中に1回だけ大狩を行うことになっていました。
これに正式に呼ばれる在地領主が武士として認定されました。
また、参加するには高度な乗馬技術と弓を射る技術も必要でした。
鎌倉武士にとっては弓こそが武士の象徴であり、魂でした。
御家人の人数はわからないそうです。史料がないためですが、著者の試算では千数百人です。
中規模の荘園の広さは二百町くらいですが、この規模の御家人はその国を代表する武士たちです。
武蔵の畠山氏、相模の三浦氏、下総の千葉氏、下野の小山氏などです。
有力武士たちを規模別にグループ化すると、トップグループは平家と源氏、奥州藤原氏などです。
第二グループは一国の支配者です。上総国の上総広常や越後国の城氏などです。
第三グループは地域の有力武士です。武蔵の畠山氏、相模の三浦氏、下総の千葉氏、下野の小山氏などです。
東国の中心は駿河、伊豆、相模、武蔵でした。いずれの地域の武士も伊豆山権現と箱根権現への信仰を共有していました。
幕府が成立したあと、政治の要職を担ったのもこの地域の武士たちでした。
四カ国以外にも有力な御家人はいましたが、鎌倉幕府の中枢に入ることはありませんでした。
こうして成立した鎌倉幕府は関東の他の諸国の有力武士たちに厳しい態度で迫ります。
そして彼らの最重要課題は土地問題の解決でした。
頼朝は御家人たちを荘園の地頭に任命し、所領の支配を認めました。
地頭の監督者として国ごとの守護を任命します。
重要なのは従来の国衙や荘園の仕組みも温存されました。
朝廷の権限を侵すことなく、一定の距離を置きながら自分たちの土地を安堵しようとしたのです。
そのため、源頼朝の権力が実質的に及ぶ範囲は東国中心でした。
鎌倉幕府が地頭を任命できたのは、東国の武士の土地と平家没官領という平家の旧領や謀反人の土地に限定されました。
第二章 北条時政の“将軍殺し”
吾妻鏡
鎌倉時代後期に成立した吾妻鏡は重要な史料ですが、欠落している部分が多くあります。
とくに将軍の末期の記事に欠落が目立ちます。
源頼朝の晩年、建久7(1196)から建久9年の記事が全くありません。
吾妻鏡が誰によって、何の目的で書かれたかを念頭に置かなければなりません。
鎌倉時代後期に幕府を動かしていたのは北条氏です。吾妻鏡は北条氏支配を正当化するための歴史書と言えます。
朝廷との関係
後白河上皇をはじめとした朝廷側は鎌倉の新政権を取り込もうとします。その最大の武器が「官位」です。
この時代、複数の実力者に仕えるのは普通のことでしたが、源頼朝は東国の武士に対して自分への奉公を第一にするよう強く求めました。
東国に生まれたばかりの政権は、朝廷により骨抜きにされると考え、東国の武士が朝廷に近づくことを警戒しました。
自分と御家人との直接的な結びつきは、これまでにない新しいものであること、それが朝廷に依拠する古い秩序と本質的に対立することを自覚していました。
その意味で最大の裏切り者になったのが源義経でした。
朝廷と距離を取ることは最重要課題だったのです。
源頼朝も朝廷との関係で手痛い失敗を経験します。「大姫入内事件」と呼ばれる事件です。
源頼朝の死後、二代将軍となったのは嫡男の源頼家でした。
「吾妻鏡」では暗君として描かれますが、なぜ排除されなければならなかったのでしょうか?
北条氏のルーツ
平家の血を引いているのは間違いなさそうですが、系図がはっきりしません。
さらに北条時政は北条家の本家の当主でなかった可能性があります。
知謀、陰謀に長けた政治家タイプだったようです。
比企氏
源頼朝が最も信頼していたのが比企氏でした。そして、頼家から実力者として重用された人物が梶原景時です。
北条時政はこの両氏を滅びすことで鎌倉幕府の主導権を握ったのです。
鎌倉時代は女性の地位が高い時代でした。頼朝の乳母の1人が比企尼でした。比企氏と頼朝一家の結びつきは強く、頼家は実母の政子のいる館ではなく、比企の館で育てられます。
頼家は比企尼の甥といわれる比企能員の娘を妻にします。
十三人の合議制
源頼家が家督を継いで3ヶ月後、建久10(1199)年、幕府は十三人の有力者による合議制を導入します。
新しい政権を作るのではなく、頼家の存在は否定しませんでした。
一方で頼家は政治への関与がこれまでのようにはできなくなります。
十三人の顔ぶれですが、文官四人(中原親能、大江広元、三善康信、二階堂行政)、他は御家人で、三浦義澄、八田知家、和田義盛、比企能員、安達盛長、足立遠元、梶原景時、北条時政、北条義時です。
十三人の合議制は強くなりすぎた将軍の権力に対する有力御家人たちの危機感の現れと考えられます。
梶原景時の失脚
十三人の合議制で将軍の力を削いだ北条時政が次に狙いを定めたのは、梶原景時でした。
梶原景時は具体的な職能がはっきりしない「侍所」の別当(=長官)を務めていました。
頼朝に重用され、頼家にも信頼されすぎたことが他の御家人の嫉妬を買ってしまった面は否めません。
梶原景時はささいなきっかけで失脚します。そして六十六の御家人が名を連ねる弾劾状が出来上がり、和田義盛と三浦義村が頼家に提出します。
頼家はかばいきれず、弾劾状を受け入れてしまいます。梶原景時は西に向かいますが、駿河国の清見関で、たまたま出くわした吉川友兼らと戦闘状態になり、梶原一族は全員討ち果たされます。
これに対して頼家も反撃に出ます。
比企氏の乱
頼家と時政の対立が深まる中、建仁3年7月に頼家が病に倒れます。
持ち上がったのが頼家の後継問題でした。
関西38カ国を弟の千幡(実朝)、関東28カ国を長男の一幡に与えようとします。
一幡は比企氏の館で育てられていました。鎌倉幕府の本拠地を一幡に与えようとしていることから、頼家と比企氏は一幡を後継者に考えていました。
一方、実朝の乳母は時政の娘のため、北条氏は実朝を将軍にしたいのです。
後継者争いは北条氏vs 頼家・比企氏の争いになりました。
最初に動いたのが、比企能員でした。しかし、すぐに北条時政の知るところとなります。
北条時政はすぐさま大江広元と相談しますが文官に相談したことが興味深い点です。
北条時政は比企能員を呼び出し、あっさりと暗殺します。そのままの勢いで比企館を襲い、頼家の嫡男・一幡も殺してしまいます。
周到な準備を行った上での暗殺劇でした。
大江広元への働きかけは解釈が難しいところですが、頼朝が組織した文官集団は取り替えが効かないものでした。
行政や朝廷との交渉の実務が切り盛りできるのは彼らだけだったからです。
比企氏滅亡の後、北条時政はすぐにでも千幡(実朝)を将軍にしたいと考えましたが、体調の悪かった頼家の体調が回復します。
一幡の死と比企氏の滅亡を知った頼家は激怒し、時政の追討を命じます。
しかしこれに対して時政は政子の計らいで病気で政務が取れないと理由づけて頼家を出家させて修善寺に幽閉します。翌年、頼家は亡くなります。
第三章 希代のカリスマ後鳥羽上皇の登場
後鳥羽上皇
後鳥羽上皇は非常に実力をもった上皇でした。
新古今和歌集の編纂でも知られ、歌人としても一流、音楽も当代きっての腕前でした。さらには武人としても名が轟いていました。
こうした個人的な能力だけでなく、経済的にも、軍事的にも強力な基礎を築きました。
理念でいえば朝廷の最高権力者は天皇であり、公地公民のため、全ての土地も住民も天皇のものであるはずです。
しかし日本社会では、地位や役職ではなく、周りが最高権力者を決めます。地位より人の社会なのです。
平安時代後期から鎌倉時代の初期においては、天皇家の家長である上皇が力を持ちました。
天皇を差し置いて政治を行なってしまうため、院政と呼ばれました。
院政はシステムでもルールでもなく、状態を示しているに過ぎません。
摂関政治が衰退した理由
平安時代の中期まで摂関政治が行なわれていました。
藤原氏が政治を司る根拠はただ一つです。それは天皇の外戚であることでした。
治暦4(1068)年、170年ぶりに母が藤原氏でない天皇・後三条天皇が誕生します。
後三条天皇は親政を復活させ、荘園整理令で正式な手続きをしていない荘園を公地に組み入れます。
これにより藤原氏は荘園の三分の一を失います。
後三条天皇が即位した時は摂関政治の最盛期を築いた藤原道長と息子・頼道のうち頼道が存命だった時です。
摂関政治は最盛期から一気に衰退するのです。
権力システムは徐々に衰退するものですが、摂関政治はシステムというのにはあまりにも不安定だったのです。
これは実態の力関係をベースとする政治の特徴をよく現しています。
院政を支えた荘園
上皇の力を支えたのは土地の主導権を握っていたからです。
後三条天皇時代に実施された荘園整理令は重大な脅威でした。その脅威から逃れるためには天皇に近い、あるいはそれを上回る権威に頼るしかありません。それが上皇でした。
後三条天皇の息子・白河天皇は上皇になると山ほどの荘園を集めます。
しかし朝廷が荘園を保有すること自体が公地公民の自己否定になります。
ですから白河天皇は自ら建てた寺の所領として行きます。いわばトンネル会社です。
「勝」のつく法勝寺など六つの寺(六勝寺)に荘園を寄進させ、莫大な富を溜め込み、院政を支えました。
後鳥羽上皇も同様に荘園経営を重要な財政基盤としてきました。
内親王を荘園領主として土地を大規模なまま維持しました。八条院領、長講堂領などが代表的な荘園です。
後鳥羽上皇は朝廷を中心とした秩序の回復という政治倫理を持っていました。それを実現するために軍事改革も推し進めます。
第四章 義時、鎌倉の「王」となる
後継者
北条時政は北条義時を後継者と考えていませんでした。義時は時政を追い落とし実力で権力を握りました。
北条時政が後継者と考えていたのは北条政範を後継者に考えていた節があります。
この頃の義時は江間姓を名乗っていました。北条家から独立していたのです。この時点で義時が北条家の当主になる可能性はありませんでした。
しかし政範は若くして病死します。
そこで今度は娘婿の平賀朝雅に権力を継がせようと考えます。
平賀朝雅
平賀氏は源義光の子・盛義を祖とする源氏の名門です。
源頼朝は父とともに最後まで行動した平賀義信を源氏一族(門葉)であり、筆頭として遇します。
理由は平賀義信の存在が真の源氏の棟梁であることを示しすものだったからです。父・義朝を知り、源氏の正統を担保する生き証人でした。
頼朝は平賀義信を最も信頼する比企氏と縁組させます。そして生まれたのが平賀朝雅でした。
義信は平賀氏を朝雅に継がせ、長男の惟義は地頭を務めた伊賀国大内荘から新たな家を創って大内惟義を名乗ります。
畠山重忠の乱
梶原景時、比企氏を滅ぼした北条時政が次に狙いを定めたのが武蔵国の秩父党を率いた畠山重忠でした。
武蔵国の国司と守護は平賀朝雅でした。平賀朝雅を後継者に考える北条時政は武蔵国を朝雅の支配地にしたいと考えていたはずです。そこで邪魔になるのが畠山重忠でした。
この畠山が鎌倉武士の鑑、理想の勇者として絶大な人気を誇っていたため、北条時政と平賀朝雅の命取りとなります。
吾妻鏡でも畠山重忠は別格の存在として描かれます。
こうした重忠のような人気者を排除するのはかなり難しいと言えます。それをわかっていたのが北条義時でした。
畠山重忠の乱は元久元(1204)年、京都で起きたある事件から始まります。
北条時政が畠山重忠の粛清を息子の北条義時と時房に相談しますが、吾妻鏡によると、義時は父・時政をいさめます。その後、引き受けることになります。
義時は一度は止めたが、親の命令だからしぶしぶ従ったというわけです。
そして重忠を討ち取ると、鎌倉に戻り、時政に報告し、言外に非難しました。
牧氏の乱
重忠を討った二か月後、時政側に源実朝を将軍から引きずり下ろし、平賀朝雅を将軍にしようという陰謀の容疑がかかります。
北条義時の軍が襲撃し、時政の館にいた源実朝を連れ出し、義時の館に移してしまいます。翌日、北条時政は執権を追われ、北条義時が執権となります。
この政変により、義時派が幕府の中枢を握ることになります。時政は出家し、鎌倉を追放され、伊豆の所領に押し込められました。
父・時政を追放すると、平賀朝雅を討ち取ります。
和田合戦
北条義時は和田義盛を繰り返し挑発します。かつて北条氏は騙し討ちなどによってのしあがあってきましたが、和田義盛とは真っ向勝負を挑みます。
建暦3(1213)年、和田義盛の挙兵を知った北条義時は、息子・泰時の活躍もあり和田氏を全滅に追い込みます。
これにより、和田義盛の持っていた侍所別当を北条氏が奪い取り、北条義時は侍所別当と政所別当を兼務することになり、政治と軍事の両方を握ることになります。
北条義時は軍事部門のトップと正面からぶつかり武力で叩き潰しました。これにより北条氏は名実とともに鎌倉幕府のナンバー1になります。
第五章 後鳥羽上皇の軍拡政策
後鳥羽上皇による軍事力増強
後鳥羽上皇が力を注いだことに一つが軍事力の増強です。
そもそも政治闘争に武士たちを巻き込んだのは後白河上皇でした。自前の武士団を組織したのは後白河上皇で、上皇の館の北側に武士たちのたまり場を作ったので、北面の武士と呼ばれました。
後鳥羽上皇は北面の武士に加えて、西面の武士も組織します。
後鳥羽上皇がスカウトに成功した武士で一番の大物は大内惟義でした。門葉(源氏一族)筆頭の平賀義信の長男で、平賀朝雅の兄です。
惟義は弟・平賀朝雅の事件に連座せず、伊勢・伊賀の守護を引き継ぎました。駿河の守護も務め、後鳥羽上皇とのかかわりも深くなります。
惟義と後鳥羽上皇との関係において重要なことが伝わっています。本来、幕府に任命された守護の惟義が、勝手に上皇の命令に従っていました。つまり、大内惟義は幕府から任命された守護であると同時に、独自の判断で上皇からの命令に従う、部下のような存在になっています。
この時代、複数の主人に使えることは珍しいことではありませんでした。しかし、源頼朝の時代、頼朝は幕府の存在基盤を揺るがすものとして、御家人が自分を通さずに朝廷の意向に従うのを極度に嫌っていました。門葉筆頭の大物御家人である大内惟義が、その禁を犯していることが重要です。
大内惟義は近畿周辺の6か国の守護に任命されていました。東西に分断する越前国、美濃国、伊勢国は、交通の面でも防衛の面でも重要です。古代の三関、北陸道の愛発関、東山道の不破関、東海道の鈴鹿関があります。
北条義時がいつ牙をむくかわからないような大内惟義に重要な防衛ラインの守護を任せたのでしょう。著者は、この守護任命には後鳥羽上皇の強力な推薦や働きかけがあったと考えています。立証する史料はありませんが、惟義と後鳥羽上皇の官家の近さや、前後の動きは、この仮説によってうまく説明できます。また、注目すべきは惟義が任じられたのは、京都の東を固めるラインでした。著者の仮説が正しければ、幕府にとって非常に危機的な事態です。
鎌倉幕府の政変の影響で、西国の守護に任命された承久武士たちは朝廷に接近していきます。北条義時が軍事と政治を独占することに対して、反発する武士も出てきます。そうした武士を取り込んだのが後鳥羽上皇でした。
後鳥羽上皇には北条義時らにまねできない武器がありました。「官位」です。関東の田舎で自分の土地を血まみれになって守ってきた武士たちにとっては大きな魅力でした。鎌倉時代になっても上位の権力によって土地の権利を保障してもらう口利き論理はなくなったわけではありませんでした。
後鳥羽上皇が大内惟義とともに頼りにしたのが藤原秀康でした。祖先は俵藤太(藤原秀郷)です。祖父は北条義時に粛清された和田義盛の弟でした。秀康の叔母は大内惟義の妻になっています。後鳥羽上皇は秀康を7か国から8か国の国司に任命します。
後鳥羽上皇の軍事編成には、平家モデルの影響が見て取れます。
承久の乱の根本原因
著者の考えでは、後鳥羽上皇に代表される朝廷の国家像と、北条義時に代表される在地領主の国家像の違いです。
後鳥羽上皇の国家観は、朝廷の伝統的な国家観です。すべての頂点に皇家があり、貴族、寺社、武士は天皇・上皇を支える存在であるというものです。
一方で、源頼朝や北条義時が考えていたのは、在地領主による在地領主のための政権でした。自分たちが実力で作り上げた東国の秩序に朝廷が介入することを嫌がりました。
この朝廷と幕府の国家観の違いが、歴史学の中世国家論の議論と重なります。前者が「権門体制論」(こちらが圧倒的な多数派です)、後者が「東国国家論」「二つの王権論」です。本書は二つの王権論の視点に立脚しています。
北条義時ら鎌倉幕府の支配範囲は東国であり、日本全体を支配する意図も実力も持っていませんでした。ですから、朝廷と全面衝突する理由はありませんでした。
後鳥羽上皇もはじめから幕府と全面対決するつもりはありませんでした。鎌倉幕府の存在を認めつつ、コントロールする自信もあったのです。切り札は源実朝でした。
後鳥羽上皇は「権門体制論」の枠組みで、自分の権力を認識していたと思われます。考えていたのは、将軍を上皇の忠実な従者とすることでした。そうすれば鎌倉の御家人たちは自分の命令に服するはずだからです。
源実朝もこうした考えに否定的でありませんでした。上皇に積極的に使えることが幕府と朝廷の正しい在り方と考えていました。そのため、後鳥羽上皇と源実朝の関係は非常に良好でした。
後鳥羽上皇は源実朝を自分の考える秩序の枠に収め切ったと考えっていたはずですが、大きな落とし穴がありました。在地領主である御家人たちとの間にギャップが生まれてしまったのです。
源頼朝はこのギャップに極めて敏感だったため、将軍になっても京都と距離を置きました。
第六章 実朝暗殺事件
建保7(1219)年1月27日、源実朝が暗殺されます。
源実朝暗殺の実行犯は公暁でしたが、古くから事件の黒幕は誰かという議論が盛んになされました。三浦義村説、後鳥羽上皇説、北条義時説などです。
著者の本命は北条義時です。事件の直前に、心身の不調を訴えて家に帰ってしまうなど、怪しい点があります。公暁の襲撃を事前に知っていたから行列に加わらなかったのではないか、と多くの人が考えました。
暗殺が起こったあと、公暁の背後関係は調べられていません。そこには最高実力者の北条義時の意図、さらには御家人の総意があったと考えています。
この頃には源実朝は北条義時をはじめとする東国の在地領主にとって扱いやすい存在ではなくなっていました。朝廷との関係において危険な存在になっていたのです。
有力御家人が平然と後鳥羽上皇に仕え、直接の指示を受けるようになります。幕府の職掌である守護の任命まで後鳥羽上皇の意向が影響するようになりました。
幕府にとって御家人統制の綻びに他なりません。その責任が源実朝にありました。
従来の北条氏の傀儡に過ぎないというイメージとは異なり、源実朝は大きな実権をふるっていました。従来の常識を覆す見解を示したのは五味文彦教授です。
実朝は政所を充実させ、将軍自らによる政治を推進しました。北条義時は助言し補佐するものの、裁判も所領の安堵も権限でした。
実権を握っている以上、御家人統制が揺らいでいる最大の原因は、源実朝にあります。
北条義時は高い官位につきませんでした。承久の乱以後、朝廷は事実上幕府の支配下に置かれます。望めばいくらでも高い官位に就くことは可能でしたが、北条氏はどんなに出世しても四位どまりでした。
そこには北条氏の明確な意志があったとみるべきです。
おそらく北条義時は官位という朝廷の序列の外側に自分たち武士を置こうとしたのです。
近藤成一氏も「鎌倉幕府と朝廷」(シリーズ日本中世史②)にて、得宗が官位上昇を遂げなかったのは、できなったというより、そもそもする気がなかったからと述べています。
源氏直系根絶やし
鎌倉幕府は自らの利益を守るため、東国武士たちが互いに強調するの仕組みだったと言えます。そのとき、源頼朝が源氏の棟梁であったことは大きな意味を持ちました。武士たちを終結させるためには、源氏の棟梁という権威が必要だったのです。
しかし、北条義時が実力で勝ち上がることにより、源氏の棟梁の必要性が薄れました。将軍はお飾りであり、もはや源実朝は排除の対象となります。
鎌倉幕府にとって源氏の役割が終わったのは、源実朝暗殺からすぐに源氏直系を根絶やしにする事件が起きたことからもわかります。
源氏の血が必要であれば、血筋を残しておいてもおかしくありません。
親王将軍をめぐる思惑
源実朝には子供がいなかったため、幕府は朝廷から養子を迎えて将軍になってもらうための準備をしていました。
北条政子が上洛し、女官・卿二位に面会し、後鳥羽上皇の皇子を将軍候補とすることが内定していました。
この位置付けは朝廷側と幕府側とでは大きく異なりました。
後鳥羽上皇からすれば、源実朝の取り込みの延長にあります。一方で、北条義時らは親王は武士ではありませんので、将軍を武士のヒエラルキーから切り離してお飾りにすることができます。
また親王将軍であれば、朝廷も幕府も天皇家をいただくものとして同格の存在になり、より独立した国家として歩む大義名分ができます。
しかし、親王将軍は実現しませんでした。源実朝の死後、幕府は親王を鎌倉への下向を要求しますが、引き延ばしの回答が来るばかりで、ついには断られます。後鳥羽上皇の幕府への不信があったためです。
後鳥羽上皇にしてみれば、いかにして幕府を抑え込むかが課題となります。手元の新たな武士団をつかって屈服させる、そう考えたのではないでしょうか。
第七章 乱、起こる
追討令
承久3(1221)年5月15日、吾妻鏡によると、後鳥羽上皇は勅命に応じて右京兆(北条義時)を誅殺せよ、勲功の恩賞は申請通りとする、という命令を各地の御家人に発します。
これが正式文書である「官宣旨」なのか、略式版の「院宣」なのか、実物が残っていませんのでわかりません。
後鳥羽上皇は北条義時を排除することだけが目的で、鎌倉幕府を否定したわけではない、という説がありますが、この時代には「幕府」という言葉時代が存在しませんでしたので、統治の主体はシステムではなく個人で捉えられていました。
ですから朝廷が幕府を倒す命令を出すときは、排除すべき指導者の名を挙げるのです。以仁王の令旨には清盛法師ならびに従類の叛逆の輩と書かれ、後醍醐天皇の倒幕の命令も平時政(北条時政)の子孫とされました。
後鳥羽上皇は北条義時が最高権力者であると見抜いており、一方で鎌倉幕府を支える御家人においても北条義時の追討令とは幕府を倒すことだという認識が共有されていました。
京都では御家人の多くが後鳥羽上皇側につきました。鎌倉では北条の館であまりにも有名な北条政子の演説が行われます。北条政子は安達景盛を介して話しかけました。
この時点で、上皇側に従うつもりなら、すでに兵を起こしているはずです。御家人たちは北条義時のもとに駆け付けたのです。
北条政子の言葉のキーワードは「恩」です。つまり土地の安堵です。鎌倉幕府は自分たちの土地を守るために自分たちで作り上げたものでした。頼朝のもとに結集したからこそ、朝廷も関東の在地領主の力を認めざるを得なくなったのです。政子はそう指摘したのです。
後鳥羽上皇の命令は、武士政権の否定です。東国の武士たちは生き残りをかけた戦いに向かうのでした。
京都進撃
北条義時には2つの選択肢がありました。鎌倉で籠城するか京都に進撃するかです。
いったんは足柄と箱根の二つの関所を固めて関東に籠城する作戦に傾いたのですが、これに異を唱えたのが文官の大江広元でした。北条政子もこれを支持し、三善康信も支持します。
幕府は東国の御家人に北条義時の奉書を伝え、出陣を命じました。幕府の勢力圏が及んだのは、遠江、伊豆、甲斐、相模、武蔵、安房、上総、下総、常陸、信濃、上野、下野、陸奥、出羽でした。三河・美濃以西は幕府の動員の外でした。
5月22日から25日にかけ、幕府軍は3つに分けれて京都を目指します。
主力は東海道で、北条時房(義時の弟)、北条泰時(義時の長男)、三浦義村らの軍隊です。東山道は武田信光、結城朝光、北陸道は北条朝時(義時の次男)です。
京都に入った幕府軍は北条泰時が5,000騎でした。二手に分かれたので、単純に倍にすると1万騎です。朝廷軍は1,700騎です。
朝廷軍は相次いで戦に負けます。京都は大混乱に陥り、6月8日には後鳥羽上皇は比叡山に逃げます。ですが、比叡山にも断られます。
6月12日になると、官軍は近江の瀬田と山城の宇治に集結させて、最後の決戦に備えます。ですが、6月13日には幕府軍に突破されます。
後鳥羽上皇が義時誅殺を命じてからわずか1か月、戦は鎌倉幕府の圧勝で終わります。
6月15日、後鳥羽上皇は北条泰時に使いを送り、全面降伏ととれる院宣を伝えます。この時、泰時の周囲にいた5,000騎のほとんどは院宣を読むことができませんでした。当時の東国武士たちの識字力はその程度でした。
院宣は完全降伏で、武力放棄を宣言していました。
武力を放棄した朝廷は政治判断や訴訟の判決などを自らの力でできなくなります。幕府と朝廷の力のバランスは圧倒的に幕府側に傾きました。
第八章 後鳥羽上皇の敗因
承久の乱を「東と西」「上と下」の軸で考える必要があります。
東と西ですが、後鳥羽上皇は西国の守護たちのほとんどを従わせることに成功しますが、幕府軍と上皇軍では動員数に明らかな差がありました。
鎌倉時代の守護の任務は「大犯三箇条」と呼ばれる3つの仕事です。1.殺人犯の逮捕、2.謀反人の逮捕、3.大番催促の権でした
3つめの大番催促は任国の武士たちに、京都の御所を警護する大番役を務めるよう促すものです。重要なのは、この仕事が戦時においては武士の招集・統率権に転嫁すると考えられるからです。
ですが、守護はあるまでも将軍から任命された役人であり、任国の武士たちは守護の家来ではありませんでした。思うがままには動かせなかったのです。
たまたま京都に来ている武士たちが朝廷軍として組織されたとみるのが実情に近かったのです。
大番役は10年に1度でしたので、その国が動員できるはずの10分の1程度ということになります。引き連れている郎党も少なく、戦意も高くありませんでした。
後鳥羽上皇は守護さえ味方につければ、その国の武士は自分の見方と考えてしまいました。国衙をおけばその国をすべて支配したと考える律令的・公地公民的論理でした。
武士たちを上からしか見られなかった後鳥羽上皇の誤算でした。
同じ守護でも西国は、源平の戦いの結果できた平家領の空白に関東の武士が赴いて守護に就任したものです。その地には何の基盤もありません。単なる守護ポストという地位の論理です。
一方で東国の武士は実力を背景に守護を務めていました。実力や人の論理です。
そして幕府と朝廷におけるリーダーシップのありかたの違いでした。
朝廷軍は現場の武士と上皇とは直接話はできませんでした。隔たりが大きければ大きいほど、上位者の権威は強大となります。権威のピラミッドが身分制に基づく朝廷型のリーダーシップでした。
対して幕府の組織原理は「御恩」と「奉公」でした。将軍と御家人の一対一の主従関係でした。
第九章 承久の乱がもたらしたもの
承久の乱後、北条泰時は京都に六波羅探題を設置し、北方を掌握します。叔父の北条時房は南方に就任します。
そして、徹底した武士の論理による処断を行いました。首謀者クラスの御家人たちの首が切られただけでなく、後鳥羽上皇の側近の貴族たちが次々と処刑されました。
貴族たちへの処断は朝廷に大きな衝撃を与えました。
そして処分は皇室にも及びます。後鳥羽上皇は隠岐配流、順徳上皇(後鳥羽上皇の次男)は佐渡、土御門上皇(後鳥羽上皇の長男)は土佐に流されます。土御門上皇は、幕府との対立を望まなかったので、無罪の可能性もありましたが、本人の希望により配流となりました。
そして天皇を退位させます。仲恭天皇を無理やり引きずりおろしたのです。
幕府の狙いは後鳥羽上皇の血統を天皇家から排除することでした。そこで、後鳥羽上皇の兄・守貞親王の息子を後堀川天皇として即位させます。天皇を幕府が決めたのです。日本史の大転換となります。
2代後、後堀川天皇の系統が途絶えてしまいます。貴族たちは後鳥羽上皇の直系を押しますが、執権・北条泰時は拒否し、土御門上皇の息子が後嵯峨天皇として即位することになります。
人事権だけでなく、荘園にも手を付けます。平家を倒した時には500か所の平家没官領が幕府のものになりましたが、承久の乱で幕府が手に入れた荘園は3,000に及びました。
これで北条政権は盤石となります。
東国中心だった幕府の支配領域を一気に全国に展開するものでした。
こうして武士の世が始まりますが、幕府が一元的に支配したわけでなく、朝廷という王権ものこり、相互作用によって歴史が動いていきます。
承久の乱から3年後、北条義時が亡くなります。継いだのは北条泰時です。泰時は法の支配を幕府に持ち込みました。律令は古すぎて使い物になりませんでしたので、新たに作ったのが貞永元(1232)年に制定された御成敗式目です。
泰時は執権の補佐役である連署、行政・司法・立法の最高機関である評定衆を設置します。執権の権力を強めるために行政機構を整えたのです。将軍の採決権は、泰時のときに執権に集約され、本格的な「執権政治」が始まります。