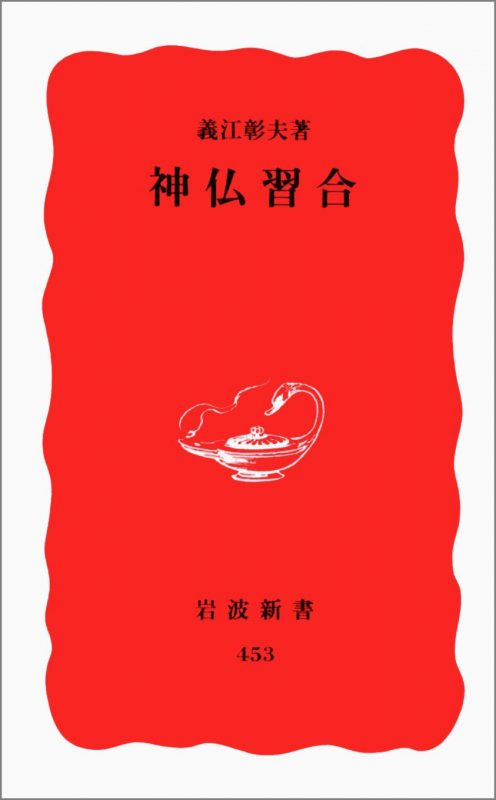明治初期における廃仏毀釈により、現在では神仏が分離しています。神社は神社で、寺院は寺院です。
ですが、日本の宗教観は、1,000年以上の長い時間をかけて、神祇信仰と仏教が融合した神仏習合がベースにあります。神仏習合は神仏混淆ともいいます。
一見すると相容れない宗教観ですが、現在でも日常的にこの影響は冠婚葬祭に残っています。結婚や出産などの慶事は神祇信仰、反対に弔事は仏教というのは、よくあることだと思います。
明治時代の直前まで、この神仏習合が当たり前の世界で、廃仏毀釈によって神社と寺院が区分されるようになると、多くの人の心の中で混乱と恐怖を巻き起こしたようです。廃仏毀釈については、安丸良夫「神々の明治維新―神仏分離と廃仏毀釈―」に詳しいです。
さて、本書では廃仏毀釈によって壊された神仏習合の成立過程を歴史学的な側面から解説したものです。宗教史的なアプローチからではないので、時代を生きた人々の精神的な変遷は追っていません。政治的・社会的背景から説明がされています。
本書によると、神仏習合の流れとして、次の各段階を踏むといいます。
第一段階:神宮寺の登場
第二段階:大乗密教の登場、その発展形としての怨霊信仰の登場
第三段階:ケガレ忌避と浄土信仰の発達
第四段階:本地垂迹説と中世日本紀の登場
歴史学的なアプローチのためなのか、古い時代の史料がないためなのか、古代において神祇信仰から仏教へ精神的な拠り所が移っていった経緯が書かれていません。
分からないことの多い時代のため想像するしかなく、学問としての歴史学が扱える領域ではなく、想像の翼を広げられる小説が扱うべき領域のためかもしれません。
普遍的宗教としての仏教と、基礎信仰としての神祇信仰という対比で、部分的には本書でも語られます。
ですが、基礎信仰と普遍的信仰が合わさっていく必然性はなく、これらが統合されるに至ったメンタリティの変遷が書かれていないので、感覚的に理解しにくい部分があります。
普遍的宗教である仏教では、罪を犯した者に対してすら最後の救いが保証されていますが、基礎信仰の神祇信仰には、救いが保証されていなかったことが、メンタリティ上の統合へのきっかけになったのでしょうか…。
神仏習合については日本史論述問題の論点(古代~奈良時代)のテーマになっています。
1998年京大:神々への信仰が神仏習合へと展開する過程と理由が問われました。
2007年の大阪大学の入試で、古代・中世において、神と神への信仰と仏教は、どのような関係にあったか、その特徴について問われました。
2015年東大:古来からの神々への信仰と伝来した仏教との共存が可能となった理由と、奈良時代から平安時代前期にかけ、神々への信仰が仏教の影響を受けてどのように展開したのかが問われました。
神仏習合の具体的事例
平将門の新皇への即位の儀式を冒頭に紹介している。ここに神仏習合の顕著な典型がみられ、興味深い内容となっている。
平将門の乱は承平5年(935年)に起き、939年に新皇に即位する。儀式は巫女によって行われた。そして、儀式において、平将門の即位を正当化したのが、八幡大菩薩と菅原道真であった。
八幡神は北九州の宇佐地方の土着信仰神。八幡大菩薩とは、菩薩のかたちをした八幡神で、仏になろうとしている神を意味する。神祇信仰における神と、仏教における神が、統合されている点で、神仏習合の典型である。
菅原道真は新皇即位の儀式の36年前に大宰府で没して、帝釈天の弟子である観自在天神に転生したとされる。神祇信仰の神(=霊魂)が仏教の神として再生した例である。
このように、神仏習合とは神祇信仰と仏教が複雑に絡んで結合したものであり、それが発展して独特な信仰となったものである。
神仏習合には段階があり、第一段階としては神宮寺の登場、第二段階として大乗密教の登場、その発展形としての怨霊信仰があり、第三段階としてケガレ忌避と浄土信仰の発達、最後の第四段階として本地垂迹説と中世日本紀がある。
第一段階:神宮寺の登場
例として伊勢の多度大神を挙げる。伊勢の多度大神は豊穣を約束する神として、伊勢、美濃、尾張などで信仰の対象となっていた。奈良時代後期の天平宝字7年(763年)に、多度大神は神であることに苦しさを覚え、苦境から脱するために神を離れ(=神身離脱)、仏教に帰依したいと託宣が降りる。
こうした神身離脱は他の地域でも起きていた。この数年前には、常陸の鹿島神宮で鹿島大神が同じような願いをし、8世紀の末頃には、山城の賀茂社の賀茂大神も、9世紀初めには、若狭の若狭彦大神も願っている。
仏教側はこの動きをとらえ、遊行する僧によって神々を仏教に積極的に取り込んだ。こうして始まった遊行僧による神々の仏教帰依運動の中で建てられたのが「神宮寺」である。神宮寺とは、仏教に帰依して仏になろうとする神々の願いを実現する場として成立した寺であった。
この背景には地方豪族層の願いがあったので、神々の仏教に帰依したいという託宣自体が、豪族たちによって仕組まれた可能性がある。
こうして始まった神宮寺は、神像安置の堂宇から始まり、本格的寺院へ発展する。神宮寺化するものの、神宮寺は朝廷に公認を得なければならない。一方で、朝廷も神道と神祇官編成から抜け落ち、仏教に傾斜し始めた地方豪族の心を捉えなおす必要があったので、承認と関与することによって、神祇離れと仏教帰依が公認されることになる。
人々は神宮寺を建立し、神による支配と生活の苦悩を脱し、仏教によって新しい繁栄を願った。
多度神宮寺の場合、本格的寺院となり、さらなる発展をするためには、国家鎮護の役割を担う延暦寺や東寺などの大寺院と接近し、その別院となる必要があった。
承和6年(839年)、多度神宮寺は延暦寺の別院となることを認められる。だが、密教色の強かった多度神宮寺と延暦寺との関係は、当初から良くなく翌年には関係が解消される。
多度神宮寺は、嘉祥2年(849年)に密教の中心寺院になっていた東寺の別院となり、この関係は近世まで続いた。
このように奈良時代後半に地方で神身離脱と神宮寺が出現したが、それより以前に王権レベルでは現れていた。
霊亀元年(715年)国家鎮護神のひとつ越前の気比神宮の神が、みずからの願いによって神宮寺を建立させている。天平18年(746年)までには九州宇佐の宇佐八幡神が八幡大菩薩と呼ばれるようになっている。天平神護2年(766年)までには、皇室祖神を祀る伊勢神宮にさえ神宮寺ができた。
王権レベルでは奈良時代初めから、諸国地域神レベルでは奈良時代後期から、神宮寺建立の動きが出ていたのである。
こうして始まった神仏習合が、続いては怨霊信仰、浄土信仰、本地垂迹説(ほんじすいじゃくせつ)、中世日本紀などへ続いていく。
とはいえ、神宮寺の登場によって本来の神祇信仰が消えることはなかった。神宮寺と神社はそれぞれの固有の役割を果たしつつ、互いに補い合う関係で存続した。
一方で、もともと仏教寺院として出発した寺では、神宮寺の動きが出る8世紀後半から、神社を勧請したり、神を守護神などにする動きがあった。
神社勧進の例では、大和の東大寺が完成前の天平勝宝元年(749年)に宇佐八幡宮を勧進している。
他には、神の祀られている近くに寺院を建立するケースもある。
最も古い例では、奈良の興福寺。平城遷都直後に王権と藤原氏の守護神を祀った三笠山(=春日大社)のふもとに建立された。以後、三笠山の神々と春日大社は興福寺の守護神とされた。
延暦寺においても、9世紀初頭に最澄が延暦寺を建てたとき、山の本来の神である日吉大神から認定をうけ、日吉大社が延暦寺の守護神となっている。
同じころ、空海が高野山に金剛峯寺を建てるとき、山の本来の神である丹生神から土地を守られる承認を得る。丹生神社は金剛峯寺の守護社となる。
こうした動きは律令国家において事は重大だった。特に全国の神々を統合する行政を委ねられていた神祇官の受けた打撃は深刻だった。
皇祖神らによって豊かに実った稲穂以下の種々のものをもって生産に励めば、霊の加護を得て豊かな収穫が期待できるとしてきた。
全国の神社から祝部(はふりべ)を集めさせたのは、こうした霊の乗り移った幣物を与えて、神々の感謝の初穂の名目で、租税を取り立てることができると考えていたからであった。
マジカルな基礎信仰を国家的に統合して、呪術的な神祇官制度を保ってきたのである
この制度は8世紀の半ば(=奈良時代の半ば)までは順調に機能していたが、8世紀後半になると神祇官に幣帛(へいはく)を取りにいかない神社があらわれはじめ、制度が揺らぎ始める。
律令国家はこの動きを絶対に認めなかった。諸国の祝部が幣帛を取りに来ないことは、存立の物的基盤である租税が取りにくい事態が生まれることを意味する。
こうした事態が8世紀後半に生じたのは、地方の神々の神身離脱と神宮寺の出現の説明となる。
神の身を脱して仏教に帰依しようとするのは、そのまま地方豪族層の苦悩でもあった。神を背負って支配してきた地方豪族がいたるところでゆきづまりに直面し、仏教に打開の道を見出し始めた時代だった。
一方で、朝廷は神宮寺化へ積極的に手を貸しながら、他方で諸国有力神社には幣帛を班給するという政策をとりつづけた。必要な妥協をとっていたのである。
9世紀半ばには遠隔地で幣帛不受理の動きが活発となる。朝廷も従来のような説得と行政罰では問題を解決できなくなってくる。やがて、この動きは畿内をはじめとした足元でも起きるようになり、制度の維持が難しくなる。
神宮寺が出現し、確立・発展する8世紀後半から9世紀後半までの100年間は、律令国家の基盤が大きく変わった時代だった。
第二段階:大乗密教との関係
空海が修行を始めたころ、密教は呪術的雑密を土台としていた。これに危機感を抱いていた空海は、体系化された密教を求め、唐に渡ってた。そして、大乗真言密教と出会い、大同元年(806年)帰国する。
帰国後、空海にはしばらく辛抱の日々が続くが、嵯峨天皇が退位する直前に、東寺を与えられ真言専修の護国寺となった。
やがて宮中御七日に御修法も真言僧が行うようになり、王権鎮護の教団となることで、王権の保護を求める諸国の神宮寺を強く引き入れる条件を整えることとなる。
そして、空海は神々を仏教に帰依させるために神宮寺を建立した満願禅師などの遊行僧の活動を継承し、雑密から大乗密教化、そして王権による庇護を実現した。
そもそも538年に仏教が伝来した際、王権は神祇信仰の外来版としか理解できなかった。そのため、偶然発生した疫病も仏教摂取による神祇の怒りとして理解していた。だが、時間が王権に仏教とは何かを理解させた。
推古朝までに芽生えていた個我と所有・支配の罪業意識は、それが生まれる以前の共同体とその神祇信仰の意識に大きな影響を与えた。仏教はそうした罪業としての所有と支配行為を承認し、正当化するものとなり、急速に広まっていく。こうして、まずは王権レベルで神の仏教帰依が始まっていく。
地方においても私的領主が生まれるにつれ、彼らの行動を支える価値観に大きな変動と迷いが生まれた。
私的領主に転化しようとしてた郡司・村長らの苦悩が、地方の大神を仏教へ帰依して菩薩となることを求めさせるようになる。
仏教は一般在俗者には、僧侶を供養し布施を施せば、贖罪と救済が保証されるという論理を持っていた。いかなる所有と支配の罪を犯しても、仏や僧への供養と布施を行えば、帳消しになるので、好都合な論理と価値観を持っていた。それゆえ、私的領主はこぞって仏教へ帰依した。
このような動きを積極的に受け止めて仏教に誘い込んだのは、教理・教学で身を固めた南都六宗の僧ではなく、民間を遊行する雑密系の密教僧侶だった。地方豪族が獲得した労働者には南都六宗ではなく、呪術と奇蹟を重んじる雑密がふさわしかった。
雑密ではじまった神宮寺は、平安時代の初めの9世紀には大乗密教を求めるようになり、普遍性をもった密教の体系を導入した大寺院に属するようになる。
この時に空海の果たした役割は決定的だった。空海のもたらした密教によって、南都六宗の寺々や、比叡山延暦寺もいやおうなしに密教を身につけなければ生き残れないと考えるようになったからだ。
真言密教の影響力は強く、延暦寺にとって体系的な密教を身に着けることは至上命題だった。そのため、延暦寺から数々の僧が中国に渡り、密教を体系的に摂取する努力を重ねることになる。円仁(慈覚大師)、円珍(智証大師)など多くの僧が渡った。
こうして平安時代前期の9世紀末までに、日本全土の寺院や神宮寺は東密、台密を中心とする大乗密教で覆われることになる。神宮寺を求める地方社会の地殻変動が、約100年をかけ、日本を密教で覆うという事態を生み出す。
第二段階の発展:怨霊との関係
王権と深く結びついた神仏習合は、10世紀にはいると、怨霊の問題に直面する。主役は菅原道真である。
醍醐天皇の下で右大臣まで上り詰めた菅原道真は、左大臣の藤原時平らによって大宰府に配流され、延喜3年(903年)没する。没後しばらくした夏の夜、道真の霊魂が尊意の住む比叡山に現れる。
この時代、死とともに怨みを持った死霊は怨霊として意識され恐れられていた。荒れ狂う菅原道真の怨霊に恐れおののき、朝廷は没直後の903年には道真に詫びて本職に復し、一階を加え、配流の宣命を焼却し、火雷天神の号を授けた。
このように、政争に敗れて非業の死をとげた人間の霊魂は、怨みをもって復讐を狙う怨霊として、畏怖と調伏の対象となった。
注目すべきは、怨霊が梵天・帝釈天という密教の神と在来の日本の神祇の双方に支えられた存在であることである。それゆえ、怨霊信仰も密教で媒介された神仏習合の一形態とみることができる。
霊魂を祀ることは、古来の神祇信仰でも行われていた。だが、それは特定の個人ではなく、共同体祖霊の群れと一体になっていた。
奈良時代半ばまでには、王権中枢部では権力抗争の末に敗死した特定の個人の霊が怨みをもって現れるという観念が生まれつつあった。
こうした観念が生まれたのは、天平元年(729年)の長屋王、天平12年(740年)の藤原広嗣など事件がきっかけである。
そして、奈良時代末から平安時代初め、これら王権反逆者の怨霊が、広範な人々によって祀られるようになる。
怨みの心を慰め鎮めながら、同時にかきたて盛り上げるような法会が行われるようになる。人々は怨霊に敬意をこめて御霊と呼んだ。これが御霊会と呼ばれるものである。ここから怨霊信仰は政治的社会運動の様相を帯びるようになる。「御霊」と最初に呼ばれるようになったのは、早良親王である。
政争敗死者の怨霊は、敗死させた個々人への贖罪と報復を求める社会的・政治的運動のシンボルへ発展した。そのさいに、密教がそれを可能にする思想的媒体になり、それゆえ陳謝する王権も仏教で対応せざるを得なくなる。
死霊は次々と御霊化され、数が増えるにしたがって、反王権的性格はますます強化されていく。
民間主催の御霊会が発展してくると、王権は対応に苦慮する。神身離脱・神宮寺化問題は、王権の神祇編成から離れようとするものではあっても、王権の支えを必要としていたのに対し、御霊会は徹底的に反王権的存在となりえたからである。
だが、ついに貞観5年(863年)王権は御霊会問題に正面から取り組まざるをえなかった。
この年は、流感が激しく多くの死者がでた。朝廷はみずから御霊会を主催する。神泉苑に崇道天皇(=早良親王)以下六前の御霊の座を設けて執り行った。
王権は御霊会をみずから主催することで、民間のエネルギーを吸収し、反逆心を護国心に転化させようと狙った。だが、民間の反逆心に満ちた御霊会を根絶することはできなかった。しばらく朝廷は毎年御霊会を主催したようだが、次第に行われなくなっていった。
王権が反逆心を護国心に転化させるのに失敗した背景には、大化前からの名族が次々と没落し、そうした名族が政争の敗死者に共鳴を覚えたこともある。神祇官のなかで藤原(=中臣)氏に実権を奪われていく忌部氏、軍事の実権を失っていった大伴氏、物部氏、王権中枢から排除されていった橘氏などである。名族の配下にいた無数の人々も犠牲をこうむった。そして、地方の旧豪族層も名族の没落とともに、力を失うことがあった。こうした人々のエネルギーを吸収しつくすまでに至らなかったのである。。
こうした時代を背景にした菅原道真の怨霊は、御霊を前史として登場した発展形としてとらえることができる。菅原道真の怨霊は、王権の非をならすのみならず、密教的理論武装が緻密で、従来の御霊の枠を踏み越えていたからである。
道真の怨霊の復讐が醍醐天皇本人にも影響を及ぼすようになると、理不尽な処置で人を死に追いやれば、霊魂は罪を犯した人すべてに報復を与え、天皇をも殺してもしかたないという認識が社会を覆った。御霊信仰に始まる怨霊の恨みは、御霊会という法会と祭祀で憂さ晴らしをする限界を超えたのだった。
偶然のかさなりを、道真の怨霊の仕業とする精神構造が時代の共通認識になり、それを可能にしたのは、仏教と神祇の双方からの支えだった。それゆえ、道真の怨霊は密教で論理化された神仏習合の発展形であったのだ。
こうして菅原道真の怨霊によって、反王権的社会運動、政治運動の要素を含んでいた怨霊信仰という名の神仏習合は、実力で王権の命を奪うと信じられるところまで達した。
時代が進み、道真の怨霊は平将門の乱を正当化するものとして登場する。この将門の乱は野望にもかかわらず、数か月で平定される。
不思議なことに、この鎮定を境にして、天神(=菅原道真の怨霊)の行動には、怒りの行動は読み取れなくなる。王権を破壊し、否定する行為は取らなくなる。
そして、王権は30年余りの歳月を費やし、天神を取り込むことに腐心し、ついには社殿や官位ねだりにまで目指すところを堕落させることに成功する。反王権のシンボルにまでなった天神は、10世紀末までに王権守護神になる。
だが、地方の武士の世界では、将門の乱を支えた道真の怨霊は、八幡大菩薩とともに、後世まで武力反逆を支える神として記憶されることになる。八幡は天神同様に神仏習合の神である。八幡神は応神などの皇祖霊であり、大菩薩は仏教である。
都では10世紀後半を通じて天神の脅威はなくなったが、反比例する形で、八坂の祇園感神院(=現在の八坂神社)に祀られる外来の架空の牛頭天王(スサノオの本地とされる)が新たな御霊として信仰されるようになり、やりばのない都の民の不満を糾合する神としての役割を果たしだす。祇園の殿舎が、祇園社と呼ばれる社殿と、感神院と呼ばれる仏堂からなっていたことからも神仏習合の観念を拠り所としているのは明らかである。
道真の怨霊を乗り切った王権は、天延2年(974年)祇園御霊会を主催し、以後これを超えようとする御霊会を抱き込むことに成功する。こうして、祇園御霊会は神仏習合の性格を堅持していくことになる。
御霊会に始まり、菅原道真の怨霊できわめ、祇園御霊会でふたたび祭りの枠内に収束していく怨霊信仰は、密教で統合された神仏習合の宗教運動であったために、幅広い振幅と柔軟性を備えた社会・政治運動でもあった。
宇多天皇、醍醐天皇の国政改革を通じ、王権は未開な共同体と公地公民の論理に立脚する律令国家から、私的領有と家産の論理に立脚した国家へ転生した。こうして奈良~平安初期に始まる私的土地所有を軸とする社会的変動は律令国家を空洞化し、権力の核を私的家産によって成り立つ新しい王朝国家を創出する。
この時代の変化の中で、共同体支配の論理を放棄できない層は没落した。9世紀末から10世紀初めを境に、諸国全般に律令国家時代に造られた郡衙が消滅してゆき、国司が荘園を没収して公領に再編していったことはこれを裏付けるものである。
この時期については、「テーマ:平安時代(藤原氏の台頭、承平・天慶の乱、摂関政治、国風文化)」にまとめています。
第三段階:ケガレ忌避と浄土信仰の発達
御霊信仰は神仏習合の第二段階を象徴的に示すものだったが、王朝国家はさらに進んだ神仏習合の諸問題に遭遇することになる。
9世紀から10世紀の間に発達する王権世界でのケガレ忌避観念の肥大化と、阿弥陀浄土信仰の日本的論理化である。
この時代のケガレ忌避観念は、人の死・産や六畜の死・産などをはじめとする特定の出来事をケガレとみなし、それに接触する機会に会ったとき、自宅の居間にひきこもって物忌みをして外出しない考えを指した。
一方で、阿弥陀浄土信仰は、極楽浄土に住む阿弥陀仏をひたすら信仰して、没後極楽に往生することを願う信仰である。
この二つが、どのような理由で神仏習合の第三段階を築くものと言えるのだろうか。
ケガレ忌避観念は、仏教の導入・定着に伴って、神祇信仰側が仏教の価値観の枠組みを取り入れ、仏教に対抗しうる新しい神祇信仰の論理として生まれたものである。日本型の阿弥陀浄土信仰は、このケガレ忌避観念を土台として日本的に変容させて、精神的支柱として定着・体系化させたものである。
そもそも王権の始祖となる神々の住む高天原は、神々の不撓の努力によりケガレが完全に排除され、至浄な世界で王権の精神的拠所になっている。そのため、神々を祭るにあたってはケガレがあってはならないという論理になり、法令にも盛り込まれるようになる。
律令国家の段階では、王権でも始祖神話の世界と、それを祭る場でしかケガレの排除を問題にしていなかった。そのため、行事の大祓いが6月の晦日と、12月の晦日の2回しか行われなかった。半年はケガレと共生せざるを得なかったのである。
だが、9世紀から10世紀になり、忌避・排除の方法も、祓除から物忌みというより厳格な道が取られるようになった。「弘仁式」でケガレの対象は特定され、忌みの日数が具体的に決められた。
制度化された物忌みは、律令国家が中国から導入した思想と制度、陰陽道がもたらしたものである。
祓えを捨てて、忌みが採用されたのは、ケガレは人に付着するものであるから、祓では十分に排除ができないと考えられたからである。完全に排除するには、時間をかけてケガレが空中に四散・消滅するのを待たねばらならないという観念が台頭してきたのである。
「貞観式」「延喜式」になると、ケガレ忌避は王権祭祀だけでなく、順次対象が広がっていき、ケガレ忌避観念が肥大化する。
ケガレ忌避観念の肥大化は、仏教に伍しうる王権固有の祭祀観念の樹立を意味し、仏教と神祇信仰は初めて対等となり、各々固有の価値観を堅持したまま共生するという神仏習合の新しい段階を築くことになる。
阿弥陀浄土信仰の隆盛も、ケガレ忌避観念と結合して日本に根を下ろしていくことになる。
厭離穢土に示されるように、この世はどこに行ってもケガレに満ちている。だからこそ、この穢土を厭い離れようではないかということになる。厭離穢土を現状認識として全面的に掲げるのは、帝王・貴族のこころをつかまえるのに最良の手立てだった。
ケガレ忌避観念を強く持っていた当時の人々は、ケガレのない世界を求める精神構造を持つ。日本の浄土信仰は、仏教が悟りと罪の背後に押しやった浄穢の観念を全面的に押し出すことで、王権と貴族社会に根を下ろした。
さらに、この思想にすがったのは、殺生を犯さざるを得ない武士・狩猟漁猟民である。殺生に携わる人々には、直接罪と贖罪を訴えて、浄土信仰を心の支えとすることに成功する。
第四段階:本地垂迹説と中世日本紀で完成を迎える
平安末期から鎌倉初期以降、本地垂迹説と中世日本紀が登場する。
本地垂迹とは、菩薩・諸天が神と化して跡を日本各地に垂れているといういみで、日本各地の神社に祀られている神々は、仏教の神仏が仮の姿をとって現れたものと理解するものである。仏教側からの神祇信仰抱き込みの説教体系である。
中世日本紀は古事記や日本書紀の神話と神々を本地垂迹説で説明しようとするものである。王権神祇信仰のよりどころである記紀神話を仏教的に解釈しなおして、仏教の世界に全面的に取り込もうとする営みとして生まれてくるものである。
王権国家完成までの仏教と神祇信仰を巡る動きは、仏教の助けを借りて神祇信仰の普遍化と論理化がすすめられた歴史であった。この延長に「往生要集」が誕生した。「往生要集」の目的は浄土信仰の本質を理解するための道を提示することであり、そのためにケガレ忌避観念を最大限に活用した。
この延長線上に全面展開したのが、本地垂迹説と中世日本紀だった。本地垂迹説と中世日本紀は仏教のイニシアチブによる神祇信仰の抱き込みであり、神仏習合の第四段階と言え、神仏習合思想の最終到達点であった。
本地垂迹説は、仏自体が積極的に神の世界に侵入して、仏の化身とみずからを位置づけるものである。この点で、決定的に神身離脱や神宮寺化の動きとは異なっている。
院政時代から鎌倉時代にかけ、全国各地の神社の神々を各々しかるべき諸仏・菩薩の垂迹した化身・権現とみなすようになる。
その結果、全国の名のある神社の本地は人々の共通認識になる。
本地垂迹説では仏教の側から日本固有の神々のすべてを包摂して化身とするという点で、神宮寺化より、はるかに仏教が上位に立っていた。積極的に仏教の論理で各地の神々の糾合したのである。
一方で、記紀神話のストーリーそのものを仏教的・密教的に説明し、作り直す営みが、王権や寺社勢力の世界で始められる。13世紀後半の鎌倉時代になると、伊勢神宮においてさえ、記紀神話を密教で解釈する動きが生じる。
鎌倉末期から南北朝をへて室町時代に至る13世紀後半から15世紀にかけては、全国の主な神社がそれぞれの立場から記紀神話を密教化していく時代である。両部神道はその論理の結実であり、それらは一括して中世日本紀と言われる。
中世日本紀は密教による王権神話の解釈の枠を超え、密教による王権神話の創造の域にまで達する。こうして、神仏習合は神仏の在来のままでの共存を前提としながら、仏教が神々の世界を包み、導き、統合するに至る。
これ以降、神仏習合は新しい展開を見せない。
本書について
神仏習合
義江彰夫
1996年
岩波新書
目次
序 巫女の託宣―誰が平将門に新皇位を授けたか
第一章 仏になろうとする神々
1 伊勢・多度大神の告白
2 神宮寺確立の過程
3 社会的背景を探る
4 律令国家の神社編成のゆきづまり
第二章 雑密から大乗密教へ
1 空海は何をもたらしたのか
2 仏教受容と密教による再編成
3 地方社会への広がり
4 王権側の論理と大寺院の対応
第三章 怨霊信仰の意味するもの
1 御霊会とは何か
2 道真の怨霊をめぐる説話
3 反王権のシンボルから王権守護神へ
4 怨霊信仰をもたらした社会的背景
第四章 ケガレ忌避観念と浄土信仰
1 王権神話が伝えるもの
2 ケガレ忌避観念の肥大化と物忌み
3 日本的浄土信仰=『往生要集』の論理
4 極楽往生を願う人々
第五章 本地垂迹説と中世日本紀
1 仏教の論理に包摂・統合された神々
2 王権神話の読みかえと創造
3 王朝国家の危機のなかで
結 普遍宗教と基層信仰の関係をめぐって
主要参考文献
あとがき