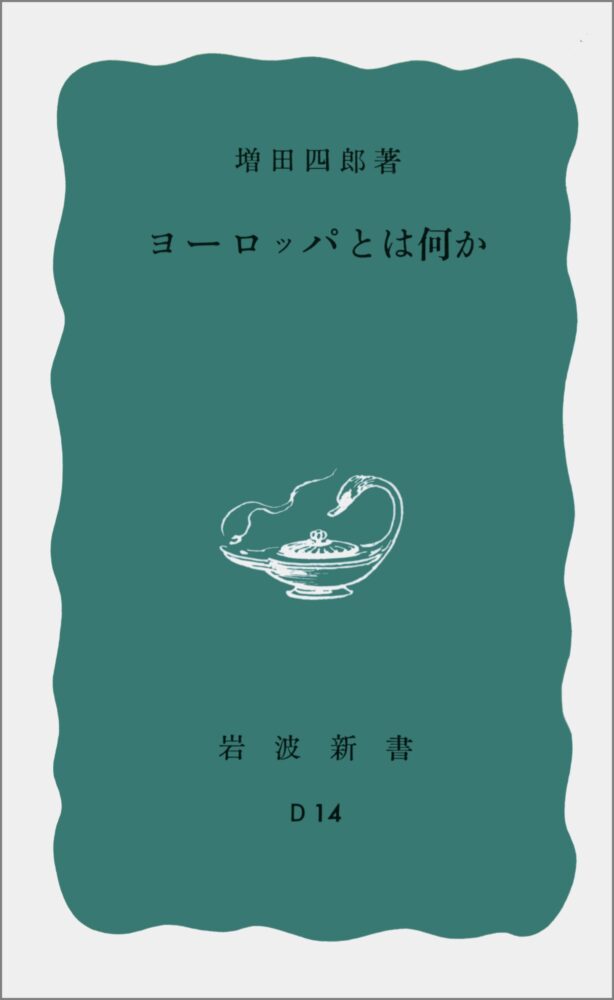覚書/感想/コメント
一九六七年の著作。本書でいちばん興味を引かれるのは、表題のヨーロッパ成立に関する歴史的な考察ではなく、十八世紀から一九六〇年代までにおける歴史学の流れであった。
特に日本では少なくとも、一九六〇年代には発展段階説が主流を占めていたようで、その中にはマルクス主義史観もあり、かなり強い影響力を占めている感じである。
本書が一九六七年に書かれているので、その後の歴史学の流れというのがわからないが、どの時点まで発展段階説やマルクス主義史観があったのかにも興味があった。
やはり一九八九年のベルリンの壁崩壊まではあったのだろうか?それとも、一九八九年以降も生き残ったのだろうか?
いずれにしても、少なくとも一九六〇年代の歴史学の流れにはマルクス主義史観を筆頭とした史観の影響があることを念頭に置いて、現在の歴史学との差違を埋めていかなければならない。
二十世紀に入ってからはアナール学派や世界システム論などの潮流もあるが、それが日本の学会にどのように影響をもたらしてきているのかに興味がある。そうした流れは別の本にて追うしかない。
本書の狙いは三つあるという。
一つは、各国別の歴史ではなく「ヨーロッパ」の成立と構造の特殊性をつかむこと。
二つは、古代世界が没落してヨーロッパ社会が成立することを、具体的に叙述することによって歴史の転換を例示すること。
三つは、日本の現状と引き比べて特色を指摘することである。
時代的には古代末期、特に初期中世のフランク王国に重点が置かれている。これはこの頃にヨーロッパの基礎が出来上がったと考えているからである。
日本の近代化において、歴史の舞台としてのヨーロッパのうごきや、そこに住んでいた人達たちの社会の紹介はなされてこなかった。
それは封建制度一つを取ってみてもそうである。日本の場合は一国内での封建制度であるが、ヨーロッパの場合は身分観や生活様式、教養、所領関係などいずれも国を超えた考え方であり制度だった。
日本の欧米の文物の取り入れ方は偏った部分が多く、いちばん見落とされてきたのは、ほかならぬ社会生活の規範であり、それがゆえに、自治体の運営が今日においてもきわめて前近代的な意識で支えられてしまっている。
日本人は家の床の間を飾ることはしても、家の前の掃除をし、町全体を清潔に保持する考えはないということだ。
ヨーロッパ諸国の学生をつかまえて、ヨーロッパとはどういうものかと聞くと、それはギリシア・ローマの古典文化の伝統と、キリスト教徒、ゲルマン民族の精神と、この三つが歴史の中の流れをどこを切っても絡み合っていると答えるのが常識である。
ひるがえって、日本でおいてアジアとは何かと聞かれた時に、同じように答えるのは不可能である。
近代歴史学に限らず、社会科学全般についていえることだが、社会科学の発達は十七、十八世紀から起き、十八、十九世紀に基礎が出来上がる。
十九世紀において世界中を一つの観点からとらえられないかと考えられ、ヘーゲルの歴史の大系にもその観点がでる。大ざっぱに全体を総括し、ヨーロッパ古代、中世とすすみ、現代が人類の最先端にあるとする理論である。
十八、十九世紀はヨーロッパが世界を制圧した時代だった。その拡大期にヨーロッパ中心の世界史観ができ、ヨーロッパ中心の基本概念が編み出された。
つまり、ヨーロッパこそが人類文化発展の頂点に立っていることを理論づけたのだ。逆に、ヨーロッパ中心の世界史観の底辺にはアフリカの未開の社会を置き、その次に一括したアジア社会の特色を持ってくる。
こうした理論は、マルクスの史的唯物論を含め、世界理論として受け入れられる情況と実力を背景にしていたから成立したのである。
日本もヨーロッパの学説に合わせて考えることが急であった。日本もヨーロッパと同じく発展をしたということにして、日本の近代化の理論的支えとし、その世界理論が日本にも当てはまると知識人が鵜呑みにし、それがいまだに強く日本の知識人に影響している。
ところが、二回にわたる世界大戦の結果、ヨーロッパの支配的な立場が崩れ、ソビエトとアメリカが重みを持つようになる。これにより、ヨーロッパ人の歴史意識を変えることになる。
歴史学では大きな問題が二つほどある。一つは、歴史研究の操作が、実証の度合いがきわめてこまかくなってきたという事実である。これによって、人類は何段階に分かれるんだという世界史の理論を打ち立てることは簡単にはいえなくなってしまった。
もう一つは、補助学の驚くべき発達である。それは考古学、比較言語学、地名学、集落史学、民俗学などである。総合的に見ていくと、十八世紀後半から十九世紀前半の学者たちが考えた発展段階説のようには、とうていいかないということがわかった。
結局、現代ヨーロッパの歴史学会の常識とは、世界理論をつくることではなく、特殊ヨーロッパ的なるものが何かを見極めることだということになっている。
マルクス主義に立った歴史学会は、こまかい実証度の高いものが出てくると、それを受け入れざるをえず、それを本質的でないと主張するためには、論証しなければならない。
アメリカ史学会では、社会学に投影された面で世界史を見ていくという歴史観である。
ヨーロッパは川で結ばれている面が強い。アルプス以北は河川こそが最大の交通網だった。
また、地理的な特性から、東から異民族が侵入してくると、西ヨーロッパ地区の東の境まで侵してくる。そのため、ヨーロッパの防衛戦は東ヨーロッパの東部ではなく、東ヨーロッパと西ヨーロッパの境界線となる山脈なり地域となる可能性が大きい。
カール大帝もオットー大帝も西ヨーロッパの東境で防いでいる。
五、六世紀から八、九世紀において歴史的世界としてのヨーロッパは形成された。古代世界の文化遺産と、カトリックの教えや諸制度、ゲルマン民族の精神が融合して民族や国家を超えたヨーロッパの基礎をつくった時期である。
それは、フランク王国は最初からカトリックの国として出発したことにはじまる。融合が起きるのは、カロリング王朝時代のことである。
本書について
ヨーロッパとは何か
増田四郎
岩波新書 約二〇〇頁
解説書
目次
はしがき
I ヨーロッパを知ることの意義
II 現代の歴史意識と「ヨーロッパ」の問題
III 地理的に見たヨーロッパの構造
IV 古代世界の没落について
V 文化の断絶か連続か
VI 転換期の人間像
VII ヨーロッパの形勢
VIII ヨーロッパ社会の特色