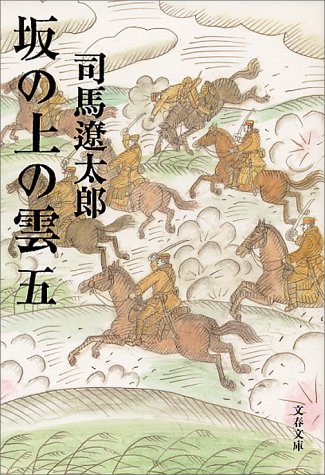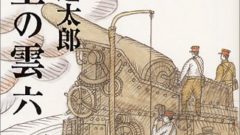文庫第五巻。
ここでは思考の硬直性というのがいかに恐いかを知らされます。
それが人命を預かる立場にあるものを襲った時の悲惨というものが、どのような結果として表現されるかをまざまざと見せつけられるのです。
思考の硬直性を代表するのは、旅順の乃木軍司令部の参謀長伊地知幸介です。
伊地知の頑迷により、作戦の転換ができないでいる旅順に、児玉源太郎が乗り込みました。
一時的に指揮権を乃木希典から借用することになるのですが、児玉源太郎が指揮権を握ってから、それこそあっというまに旅順攻略の道筋がたちます。
それは、二〇三高地攻めからはじまりました。
この場面で司馬遼太郎氏は、前の四巻から続く怒りというのを、児玉源太郎の口を通じてぶちまけています。
児玉源太郎は二〇三高地の占領を確実にするために、二十八サンチ砲での援護射撃を加えることにしました。
この援護射撃は難しく、味方もろともに粉砕してしまう恐れがあります。
それを砲兵の中佐が指摘し、『陛下の赤子を、陛下の砲をもって射つことはできません』といったあとの場面です。
『児玉は突如、両目に涙をあふれさせた。この光景を、児玉付の田中国重少佐は、生涯わすれられなかった。児玉はかれなりにおさえていた感情を、一時に噴き出させたのである。
「陛下の赤子を、無為無能の作戦によっていたずらに死なせてきたのはたれか。これ以上、兵の命を無益にうしなわせぬよう、わしは作戦転換を望んでいるのだ。-(略)-」
-(略)-
「-(略)-二〇三高地の西南の一角に、百名足らずの兵が、昨晩から貼りついているそうだ。かれらは歩兵の増援どころか、砲兵の援護もなく、ただ寒風にさらされて死守しているらしいという。その姿を、この場にいる者で見た者があるか」
児玉は、一座を見まわした。おどろくべきことに、この軍司令部では、軍司令官をはじめ、その幕僚のたれもが、その光景を見に行った者がないのである。』
また、別の場面。
児玉が第七師団司令部で精緻に戦況を知ろうとして、第七師団の参謀に攻撃正面の地図を書かせました。
ですが、その地図の上では、同じ中隊が左翼にも右翼にもいることになっています。
やがて師団参謀の書き間違えであり、現地を知っていない証拠でした。
『それだけに、地図をのぞきこんでいる児玉の怒りはすさまじかった。
(この連中が人を殺してきたのだ)
とおもうと、次の行動が、常軌を逸した。-(略)-その金色燦然たる参謀懸章をつかむや、力まかせにひきちぎった。
「貴官の目は、どこについている」
とどなった。つぎの言葉が、長くつたえられた。
「国家は貴官を大学校に学ばせた。貴官の栄達のために学ばせたのではない」』
上記と同じような場面を、今度は秋山好古を登場させて、再現しています。
それは、黒溝台戦が済んだ後、秋山好古が松川敏胤と馬をならべて騎行したときのことです。
黒溝台におけるほとんど敗戦ともいうべき戦いの原因を作ったのは、総司令部の作戦能力にあるのではないかと思っていた好古は、婉曲に松川を詰問しました。
ですが、松川敏胤は作戦家の通弊で、自分の作戦の誤りをみとめたがらなかったようです。これに対して好古はきつい言葉を返しています。
さて、秋山真之はよく「自分は新時代のうまれだから」と言ったそうです。
新時代とは、真之が明治元年うまれという意味であり、自分たちの頭が新しいというよりは、むしろ卑下する時に使ったようです。
武士というものがなくなる時代に生まれたため、武士的な素養をあまり身につけていません。
彼と同世代の連中は、旧式な人間を軽侮する一方で、典型的武士蔵というものへのあこがれをたいがいもっていたそうです。
小説(文庫全8巻)
NHKのスペシャル大河「坂の上の雲」(2009年~2011年)
内容/あらすじ/ネタバレ
旅順の乃木軍司令部から児玉源太郎のもとに入ってくる報告は、負けたとは書かれてはいないものの、ことごとく敗報であった。児玉は旅順で無益に殺されてゆく兵士たちが、哀れで、座に耐えられなかった。
児玉は旅順に行くことにした。乃木のかわりに第三軍を指揮しに行くという。これは軍隊の生命とでもいうべき命令系統の破壊を意味する。児玉はそんなことは分かっていたが、秩序を守って日本を滅ぼしていいのか、今のままでは旅順のせいで日本は潰れてしまう。児玉は軍法会議にでもなんでもかけられていいという肚がある。
一つの懸念がある。それは乃木が自分を拒んだ場合である。そのためにも、児玉は大山巌の秘密命令を得て旅順に向かうことにした。できればこの秘密命令を出して乃木から指揮権を奪いたくはない。
児玉は二〇三高地を攻めるつもりでいた。
これより二日前、乃木希典は作戦思想を修正し、攻撃の力点を二〇三高地へと向けようと決心した。軍司令官独自の判断であり、参謀長の伊地知幸介の発議によるものではなかった。乃木希典は開戦以来はじめて参謀長の意向を無視したのだ。だが、二〇三高地はすでにあらゆる砲塁のなかで最強のものになっていた。
ロシア軍の銃砲火の中で、日本軍の死の突撃の反復の結果、奇蹟が現出した。一時的にしろ、二〇三高地を占領することができた。この前日の朝、この方向の将帥である大迫尚敏は、二〇三高地を展望できる高崎山に登り、戦況を見た。そばの一曹長は、これは地獄だ、とつぶやいたという。全山を日本兵の死体がびっしりと覆っていた。
汽車に乗っていた児玉に、二〇三高地が陥ちたとの報が届いた。児玉は祝杯を挙げる準備をさせたが、やがて、それが一時的なものでしかないのを知り、激怒する。報告では「占領セリ」とあったため、児玉は戦争の完結もしくは戦闘行為の終了を意味するととらえた。報告に問題があったのだ。
予定通り児玉は行くことにした。その児玉を出迎えたのは参謀副長大庭二郎中佐だった。
児玉は伊地知に会うと、乃木軍司令部の作戦について痛烈な批判をし始めた。凄まじい罵倒で、熟語の要約すれば、無能、卑怯、臆病、頑固、鈍感、無策といったふうのものであった。
この場には乃木はいなかったが、児玉にしてみれば、指揮権を奪う乃木がこの場にいなくてよかった。乃木と児玉は若い頃からの友人であり、できるだけその名誉を傷つけたくなかった。だから、児玉は乃木と二人きりで話がしたかった。指揮権は乃木から児玉に移った。
児玉は作戦の大転換をすることにした。そして幕僚を集め「以下は命令である」と告げた。一座のものは動揺した。児玉は大山の幕僚に過ぎず、乃木軍の幕僚に対する命令権は持っていない。それが命令をするのは統帥権の無視であったが、児玉は無視した。そして、つづけて「攻撃計画の修正を要求する」といってしまった。本来なら乃木がいうべき言葉である。
児玉は二〇三高地の占領確保のため、重砲隊を移動して高崎山に陣地変換し、椅子山の制圧に乗り出すといった。そして、二〇三高地占領の上は、二十八サンチ榴弾砲をもって、連続砲撃を加える、と付け加える。
砲兵の中佐や少佐が不可能だと反対意見を述べたが、児玉は信じなかった。それには前例があったからである。そして、児玉のいうとおりに二十四時間以内に重砲は二〇三高地の正面に移された。
十二月五日、陣地移動を完了した攻城砲は早暁から砲撃を開始した。そして、児玉の重砲陣地の大転換はみごとな功を奏しつつあった。攻撃開始から占領までに要した時間はわずかであり、まるで魔術を使ったような、嘘のような成功であった。午後二時、二〇三高地占領はほぼ確定した。
児玉は山頂の将校に向かって電話した。「旅順港は、見おろせるか」「見えます。各艦一望のうちにおさめることができます」
児玉の作戦は奏功した。あとは、二十八サンチ榴弾砲で、二〇三高地越えに軍艦を射つことである。命中精度は、百発百中であったといってよかった。
児玉は乃木から指揮権を奪った。このことは部外に洩らすべからざるものであり、すべての功績は乃木希典に帰すべきである。でなければ、児玉のやったことは、すさまじい悪例として残ることになる。
二〇三高地が陥ちたことが、日本軍をあれだけ苦しめた旅順要塞にとって致命傷となった。
おもえば、海軍が海上から発見した二〇三高地という大要塞の弱点を乃木軍司令部が素直に認めて、東京の陸軍参謀本部が海軍案を支持したとおりにやっておれば、旅順攻撃での日本軍死傷六万という膨大な数字を出さずに済んだであろう。
児玉の旅順における用はすんだ。
東郷艦隊は開戦以来十ヶ月海に浮かびっぱなしである。二〇三高地の制圧は朗報であるものの、ロシア艦隊の一隻でも撃ち洩らせば困ることには変わりなかった。
唯一残っていた戦艦セヴァストーポリは、中佐に昇進していた秋山真之がしめしたように、水雷艇で沈めた。この沈没は東郷平八郎が自ら確かめに行った。
そして、沈んでいるセヴァストーポリを見て、無口な東郷が「沈んでおります」といった。これによって、十ヶ月におよぶ封鎖作戦にピリオドが打たれることとなった。
この後、東郷は乃木を訪ねた。それは、二〇三高地をおとしてくれた礼と、乃木が二児を戦死させたことについての弔意をのべるということがあるであろう。
東郷艦隊は第三艦隊を残して引き上げることになった。
秋山真之も東郷らとともに東京に戻った。船がドックに入っている間、船乗りにとっては休養期間である。この間、真之はひたすら対バルチック艦隊の作戦を練っていた。そして、真之が建てた原則は「七段構えの戦法」であった。かつて小笠原長生から借りた日本水軍の古戦法から発想したものであった。それが果たして効果があるのかを、真之は検証していた。
後に「七段構え」と呼ばれる迎撃戦法以外に、敵を一艦残らず沈める方法はなかった。済州島からウラジオストックの沖までの海面を、七段に区分して、区分ごとに戦法を変えるのだ。
この頃、「ロジェストウェンスキー航海」といわれるバルチック艦隊の苦難の航海は、アフリカ大陸のはしにさしかかったばかりであった。
苦難の航海となった理由は、その長い航海の大半の港がイギリスによって握られているか、その影響下にあることであった。イギリスと日本は同盟しており、そのことによってイギリスは国際法の許すギリギリにおいてバルチック艦隊の航海を妨げようとし、艦隊を疲弊させようとしていた。そして、何よりも苦しめたのは、艦隊にとって不可欠な石炭の積み込みであった。これがイギリスの妨害によって思ったようにいかなかった。
バルチック艦隊の士気は衰えはじめ、各艦に故障が続出し、徴用された火夫たちの小さな反乱や、あげくはロジェストウェンスキー自身が海の上で迷子になるなど散々たるものだった。
旅順が降伏した。降伏した時、旅順要塞には数量的には一月から二月以上は戦える兵力と物資を保有していた。降伏はステッセルの一己の決断によりでた。
旅順における両軍の兵員の損害は、ロシア軍の兵力四万五千、うち死傷は一万八千余、さらにこのうちで死んだものは二、三千人だったのに対し、日本軍は兵力十万、うち死傷は六万二百余、さらにこのうち死んだものは一万五千四百余であった。日本の六割の損害というのは世界戦史上でもまれな数字となった。
バルチック艦隊はマダガスカル島に着いた。ここのノシベという漁港に二月ほど放置されることになる。本国からの指令が来ないので、身動きがとれないのだ。バルチック艦隊には、旅順の陥落が伝わっている。
この艦隊の戦略的価値は旅順艦隊と合流して日本艦隊を撃滅することになるもので、孤軍となっては仕様もない。この場合、原理の基盤が崩れた以上、本国へ帰るべきであった。だが、本国からの指令が来ない。
この頃、本国では、老朽艦隊をかき集めてもう一艦隊を作ろうと考えていた。そのため、バルチック艦隊をノシベに待たせることにした。
沙河の線で戦線が凍結している。そして文字通りの冬営をしている。
日本軍の兵力は十二個師団相当しかない。一方のロシアは十七個師団を持ち、さらに大動員することで二十八個師団まで増やそうとしていた。
クロパトキンはグリッペンベルグ大将に押し切られるかたちで、攻勢に出ようとしていた。だが、日本の満州軍総司令部は、そんなばかなことがあるかという態度で終始した。この厳冬期に、大兵力の運動はできないというのが唯一の理由であった。参謀松川敏胤大佐がとりつづけた態度であり、児玉源太郎も信じた。
だが、ロシアがかつてナポレオンを撃破したのは、冬季であり、かれらの運動は冬季において得意であった。
日本軍の最左翼を受け持つ秋山好古は騎兵による敵情捜索によってこの動きを察知していた。このことごとくを司令部に報告したが、松川敏胤は、また騎兵の報告か、とほとんど一笑に付し、一度といえども顧慮を払わなかった。
日本軍の陣の中でもっとも薄い秋山好古の守る最左翼に、ミシチェンコ中将とその騎兵集団が襲いかかろうとしていた。
そして、ようやく、日本軍総司令部はミシチェンコ中将が営口付近の兵站基地を襲おうとしていることに気づいた。
この間、秋山好古もミシチェンコと類似した長駆作戦をロシア軍の後方で行った。
本書について
目次
二〇三高地
海涛
水師営
黒溝台
関連地図
登場人物
秋山信三郎好古…兄
秋山淳五郎真之…弟
季子…真之の妻
児玉源太郎…参謀次長
田中国重…少佐、のち大将
乃木希典…第三軍
伊地知幸介…参謀長、少将
大庭二郎…中佐、参謀副長
佐藤鋼次郎…砲兵中佐
奈良武次…砲兵少佐
大迫尚敏…中将、第七師団長
松村務本…中将、第一師団長
志賀重昴
黒井悌次郎…海軍中佐
有賀長雄
大山巌…参謀総長
井口省吾…少将
松川敏胤…大佐
黒木為楨…陸軍大将、第一軍
藤井茂太…参謀長
奥保鞏…第二軍
落合豊三郎…参謀長
梅沢道治…少将
東郷平八郎…中将、連合艦隊司令長官
島村速雄…連合艦隊参謀長、のちに元帥
飯田久恒…少佐
長岡外史…参謀本部次長
(秋山支隊)
永沼秀文…中佐
ニコライ二世…ロシア皇帝
ウィッテ…ロシアの重臣
ステッセル
コンドラチェンコ…少将
トレチャコフ…大佐
フォン・エッセン…大佐
レイス…大佐
クロパトキン
グリッペンベルグ…大将
ミシチェンコ…コサック騎兵集団の長
ロジェストウェンスキー…中将、バルチック艦隊司令長官
フェリケルザム…少将